「孫のいない人に孫の話はタブー」と感じたり、検索したことがある方は少なくありません。
近年、家庭や人生のあり方が多様化する一方で、シニア世代を中心に「孫がいる=幸せ」「孫がいるのは 勝ち組?」といった価値観が根強く残っているのも現実です。
そのような中で、孫の話題が日常会話に頻繁に登場することに、違和感や疎外感を抱いている人もいるのではないでしょうか。
そもそも、孫がいないのはみじめなの?といった考えは、過去の固定観念に基づいた誤解に過ぎません。
孫がいない人の気持ちは、単なる羨望や寂しさでは語りきれない繊細な背景を持っています。そして、「孫の話は他人は興味なし」と感じる場面があっても不思議ではありません。
本記事では、周囲との関わり方や対処法、そして「孫自慢における心理」や「ハラスメント」と受け取られかねない発言のリスクについても解説します。
さらに、「孫が生まれたの?と聞かれたら話せばよい」という考えや、孫がいる側も気づかいが必要であることについても触れながら、誰もが心地よく過ごせる会話のあり方を考えます。
会話の中で大切なのは、自分の思いを押しつけることではなく、相手の立場を尊重することです。そのためには、年齢に関係なく「コミュニケーション力をつけよう」という意識が不可欠です。
この記事を通じて、立場の違いに配慮した思いやりある対話のヒントを見つけていただければ幸いです。
孫のいない人に孫の話はタブーとされる理由

- 孫がいない人の気持ちを理解する
- 孫がいないのはみじめなの?という誤解
- 孫の話は他人は興味なしという現実
- 孫がいる側も気づかいが必要
- 孫が生まれたの?聞かれたら話せばよい
孫がいない人の気持ちを理解する
孫がいない人の気持ちを理解するためには、「当たり前」だと思われてきた価値観にまず目を向ける必要があります。
かつての日本では、結婚して子どもを産み、さらに孫ができるという流れが「標準的な人生」とされてきました。
しかし現在は、未婚率の上昇や多様な生き方の尊重により、子どもを持たない人生、孫のいない人生も特別なものではなくなっています。
とはいえ、社会の価値観が完全に変わったとは言えません。
たとえばシニア世代にとって「孫の有無」は、人付き合いの中で暗黙のステータスになりがちです。
会話の中で「お孫さんは何人?」といった質問が何気なく出てくることもあります。このような場面で、孫がいない人は「自分は普通ではないのか」と疎外感や寂しさを感じてしまうことがあります。
さらに、周囲が孫の話題で盛り上がっているとき、自分にはその会話に参加する資格がないように感じることもあるでしょう。
無理に興味のない話題に合わせる必要はありませんが、その場の空気を壊さないようにする配慮が求められること自体が、心の負担になることもあります。
これを理解するには、ただ「かわいそう」と思うのではなく、孫がいないこと自体を「欠落」や「不幸」とみなす見方をやめることが大切です。
人それぞれに事情があり、どんな家族の形にも価値があります。
多様性を受け入れ、相手の立場に立って言葉を選ぶことが、これからの社会に求められる思いやりではないでしょうか。
孫がいないのはみじめなの?という誤解

「孫がいない=みじめ」というイメージは、根強い偏見の一つです。しかし実際には、そのような見方は古い価値観に基づいた誤解です。現代では、孫がいない人生を選択する人も増え、それが劣った生き方だとは言えません。
たとえば、子どもが結婚していなかったり、そもそも子どもを持たない選択をしていたりすることは、決して珍しいことではありません。
また、子どもがいてもさまざまな事情から孫がいない家庭も多くあります。
こうした背景を無視して、「孫がいないのはかわいそう」「寂しいに違いない」と決めつけるのは、大変失礼なことです。
一方で、周囲との温度差を感じることで、本人が孤立感を抱くことはあります。とくに、高齢になると話題の中心が家族や孫に偏りがちです。その中で、共感できない話題ばかりが続くと、「自分はみじめなのかもしれない」と思い込んでしまう人もいるかもしれません。
このような誤解を防ぐには、まず他人と自分を比べないことが重要です。
人生の価値は、孫の有無で測れるものではありません。旅行や趣味、ボランティア活動など、孫がいなくても充実した毎日を送っている人はたくさんいます。
また、「子どもや孫の世話に追われず、自分の時間を大切にできる」という考え方もあります。
つまり、「みじめ」という言葉自体が的外れです。他人が勝手に貼ったレッテルに惑わされず、自分のペースで豊かな時間を過ごしている人も大勢いるのです。
孫の話は他人は興味なしという現実
孫がいる人にとっては、日々の成長やエピソードが何よりも喜ばしい話題であり、話したくなる気持ちはよくわかります。しかし、聞き手がその話に興味を持っているとは限りません。
特に、孫のいない人や家族との関係に悩みを抱えている人にとっては、孫の話は苦痛になりかねません。
このように言うと冷たい印象を持たれるかもしれませんが、そもそも「他人の孫の話」は、基本的には個人的な話題です。
写真や動画を見せられても、相手がその子どもを知らなければ反応しようがありません。
それにも関わらず、会うたびに孫の話を繰り返すと、話の押しつけになってしまう恐れがあります。
もちろん、日常の一部として自然に出てくる程度なら問題ありません。
ただし、相手の反応を無視して延々と自慢話を続けるのは、会話のキャッチボールとは言えません。
特にLINEなどで頻繁に写真や動画を送ってしまうと、相手は返信に困るばかりか、心の距離を置くようになる可能性もあります。
こうして、孫の話が会話の中で浮いてしまう理由は明らかです。「話したい」気持ちだけでなく、「相手は聞きたいと思っているか」を考える意識が欠けているからです。
誰かと心地よく関係を続けたいと思うなら、自分の話題がどのように受け取られるかに目を向ける必要があります。
自慢話ではなく、共通の関心や相手の立場に寄り添った内容を意識すること。それが信頼されるコミュニケーションの第一歩になります。
孫がいる側も気づかいが必要
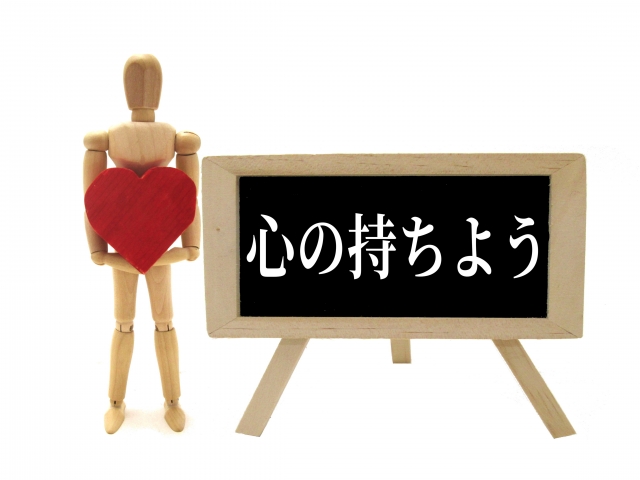
孫がいること自体は喜ばしいことですが、それを周囲にどう伝えるかには慎重さが求められます。というのも、誰もが同じような家族構成や環境にあるわけではないからです。
子どもがいない人、子どもが結婚していない人、孫ができる見込みがない人など、さまざまな事情を抱える人が身近にいる可能性は十分にあります。
だからこそ、話す側には配慮が必要です。
会話は一方的な発信ではなく、相手との関係性の中で成り立つものです。
たとえば、LINEで孫の写真や動画を連続して送る行為は、見る側にとっては「自慢」と捉えられることもあります。
たとえ悪気がなかったとしても、「興味がない」「返信に困る」といった感情を引き起こしてしまうことは珍しくありません。
それでは、どうすれば良いのでしょうか。
まずは、相手がその話題を歓迎しているかどうかを感じ取ることが第一です。
「孫ができた」という話題も、あくまで相手から聞かれたときに話すぐらいの距離感が理想的です。
話したい気持ちがあるなら、「少しだけ孫の話をしてもいい?」と一言添えるだけでも、相手に配慮している印象になります。
また、自分と違う境遇にある人との会話では、共通の話題を見つける工夫も有効です。
趣味、最近読んだ本、地域の出来事など、誰もが入りやすい話題を選ぶよう心がけるだけでも、関係は円滑になります。
会話のバランスを意識することで、相手に余計な負担をかけることなく、良好な人間関係を保つことができるでしょう。
孫が生まれたの?聞かれたら話せばよい

「孫が生まれたの?」と尋ねられたときには、素直に答えても問題ありません。むしろ、聞かれたことに対して自然に答える姿勢は、良好なコミュニケーションにつながります。
ただし、そのまま勢いよく話し続けるのではなく、相手の反応を見ながら適度な長さにとどめることが大切です。
このとき注意したいのは、相手が関心を持っているのか、それとも社交辞令で聞いたのかを見極めることです。例えば、相づちが曖昧だったり、話題を変えようとしているようであれば、それ以上は深く踏み込まない方が良いかもしれません。
また、「話したい」気持ちが先行して、話題がエスカレートしてしまうケースもあります。
写真や動画を見せたり、育児エピソードを長々と話すことは、聞き手が孫に興味を持っていない場合には負担になります。
こうした行動は結果として、会話を一方通行にし、人間関係にひびを入れてしまう可能性があるのです。
これを避けるためには、「自分が話したいこと」ではなく、「相手が聞きたいこと」に意識を向けることが重要です。
たとえば、「写真を見せてもいい?」と一言断るだけで、相手が受け入れる姿勢かどうかを確認できます。こうした小さな配慮が、思いやりある関係を築くための鍵となります。
言ってしまえば、話すべきかどうか迷ったときには「相手から聞かれたら話す」が基本。
無理に話題にしようとするよりも、その自然な流れを大切にすることで、穏やかなやりとりが続けられるでしょう。
孫のいない人に孫の話はタブーとされる社会背景
- 孫がいるは 勝ち組?という価値観の危うさ
- 孫自慢心理にある承認欲求
- 対処法としての距離のとり方
- ハラスメントと受け取られることも
- コミュニケーション力をつけよう
孫がいるは 勝ち組?という価値観の危うさ
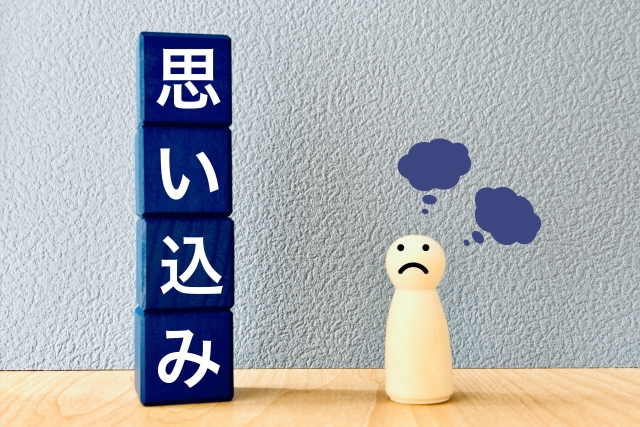
「孫がいる人は勝ち組」といった考え方は、今の時代にはそぐわない価値観です。
なぜなら、それは無意識のうちに「孫がいない人は負け組である」と暗に示すことになるからです。家族のあり方や人生の幸せは人それぞれであり、画一的な基準で測れるものではありません。
一方で、世代によってはこのような価値観が根深く残っていることも事実です。
特に高齢者層では、子どもが結婚し、孫ができることが「一人前」とされてきた背景があります。
そのため、自分が孫を持てたことを自然と誇りに感じ、それが他人にも共有すべき「良いニュース」と信じて疑わない人もいます。
しかし、現代は晩婚化や非婚化が進み、そもそも結婚や出産を選ばない人が増えています。
また、不妊治療やパートナーの問題など、本人の意志とは関係なく孫を持てない人も多く存在します。
そのような現実を無視して「孫がいてこそ幸せ」と声高に語ることは、相手を傷つけたり孤立させたりするリスクを伴います。
さらに、孫を持つこと自体も一種の「偶然の結果」であり、努力でどうにかなるものではありません。それをもって優越感を抱くのは、非常に不公平な考え方とも言えるでしょう。
このような背景を理解したうえで、人との関わり方を見直すことが大切です。
孫がいることを喜ぶのは自然なことですが、それを「勝ち」と表現するのではなく、あくまで個人的な幸せの一つとして扱うべきです。
周囲の人との健全な関係を築くためにも、自分の価値観を押しつけず、他者の立場に立った言動を心がけたいものです。
孫自慢心理にある承認欲求

孫自慢をする人の多くは、単に喜びを共有したいだけではなく、心の奥に「自分を認めてほしい」という承認欲求を抱えていることがあります。
これは人間にとってごく自然な心理であり、特に高齢になるほど他人との比較や人生の成果を実感したくなる傾向が強くなります。
例えば、退職後に仕事上の肩書きや役割がなくなったとき、自分の価値を感じにくくなる方が多くいます。そのような中で「祖父母になった」という新しい立場は、自分の人生が順調だった証として実感しやすく、誇りに思える要素になるのです。
さらに、孫が可愛いという気持ちに加え、「自分の子どもがしっかりしている」「良い家庭を築いている」ということまで評価されたいという思いが背景にあることもあります。
この心理が無意識のうちに強く働くと、会話の中に頻繁に孫の話題を盛り込んだり、聞かれてもいないのに写真や動画を見せるという行動につながります。
相手の興味や状況に関係なく、ひたすら自分の話を続けてしまうのは、承認欲求が過剰になっているサインとも言えます。
一方で、承認欲求そのものは否定されるべきものではありません。誰にでもあるものだからこそ、それに気づいてコントロールする意識が大切です。
自分の話ばかりになっていないか、相手が楽しめているかを振り返るだけでも、会話の質はぐっと良くなります。
つまり、孫自慢の裏側には、「私はまだ誰かに認められたい」という切実な気持ちがあるのです。その気持ちを理解したうえで接することで、不快に思わずに済むこともあるかもしれません。
対処法としての距離のとり方

孫自慢にどう対処すればよいか悩んでいる人は少なくありません。特に、相手が身近な親族や長年の友人であればあるほど、強くは言いにくく、関係を壊したくないという気持ちが働くものです。このようなとき、無理に我慢を続けるのではなく、適切な距離のとり方を身につけることが有効です。
まず、毎回同じような孫の話を聞かされる場合は、会話の時間や頻度をコントロールする工夫が必要です。たとえば、LINEで大量の孫の写真が送られてくる場合には、通知をオフにする、返信を必要最低限に抑えるといった方法があります。
また、会話の流れが孫の話題に偏りそうなときには、自分の趣味や最近の出来事をさりげなく話題に持ち込むことで、空気を切り替えることもできます。
それでも繰り返し自慢が続く場合には、「最近、忙しくてスマホを見る時間が少ないの」といったやんわりとした表現で距離を置くことも一つの方法です。
直接的に「もう送らないで」と言うのは気が引けるかもしれませんが、自分の負担にならない範囲で相手との接点を減らしていくことは、十分に正当な対応です。
ただ、相手が悪意なく話している場合も多いため、あまり強く否定しすぎると逆に気まずさが残ることもあります。だからこそ、自然な距離感を保ちながら、感情的にならずに接する姿勢が大切です。
要するに、無理をせず、自分が疲れない関係性を保つことがポイントです。相手に合わせすぎず、穏やかに距離を取ることで、精神的なストレスを軽減しつつ良好な関係を維持することができます。
人との会話で気を遣いすぎて疲れたときは、少し一人の時間をとるのも大切です。
私はそんな時、香りのよいハーブティーを入れて、気持ちを落ち着けるようにしています。
ハラスメントと受け取られることも
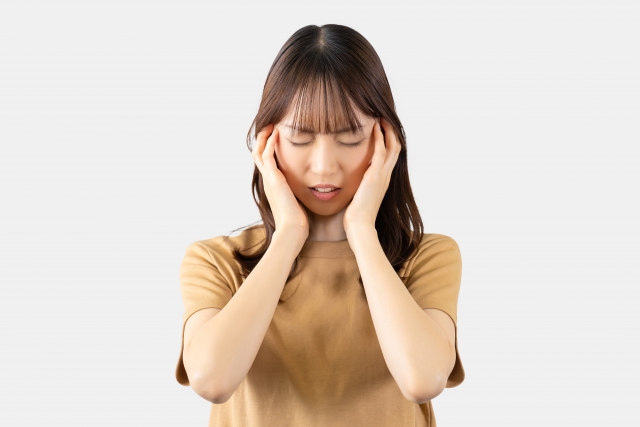
孫の話を繰り返す行為が、相手によっては「ハラスメント」として受け取られることがあるのをご存知でしょうか。これは「孫ハラスメント(孫ハラ)」とも呼ばれ、近年ではネットやカウンセリングの場でも頻繁に取り上げられるようになってきました。
本来、ハラスメントとは、本人にそのつもりがなくても、相手が不快に感じたり精神的に負担を覚えることで成立する行為です。
つまり、「喜びを共有したい」という善意や親しみの気持ちであっても、それが一方的であれば、結果として相手を傷つけてしまう可能性があります。
特に、子どもがいない人や、子どもがいても結婚や出産の予定がない人にとって、孫の話題はデリケートなものです。
「まだなの?」「早く孫の顔が見たいね」といった言葉は、聞く側にとってプレッシャーになるだけでなく、過去のつらい経験やコンプレックスを刺激してしまうこともあるのです。
さらに、会うたびに孫の話をされ、毎回同じようなエピソードを聞かされると、「またか」と思ってしまう人もいます。
それが蓄積していくことで、やがて「話すのが嫌」「会いたくない」といった気持ちへと発展するケースも少なくありません。
このような背景があるため、孫の話をする際には、相手の表情や反応をよく観察することが求められます。また、頻度やボリュームを考えたうえで話すようにすれば、トラブルを防ぐことができます。
つまり、孫自慢もやり方を間違えれば、無自覚なハラスメントになり得るということです。
大切なのは、自分の気持ちばかりでなく、相手の心の状態にも想像を巡らせること。そうした配慮が、より良い人間関係を築くうえで欠かせない要素となります。
コミュニケーション力をつけよう

人との関係をより良いものにするためには、年齢に関係なく「コミュニケーション力」を意識して育てることが大切です。
特にシニア世代になると、家族や友人との会話が日常の楽しみの中心になることが多く、会話のあり方が人間関係の質を左右することがあります。
コミュニケーション力とは、単に言葉を交わす技術だけを指すのではありません。
相手の表情や反応から気持ちを読み取ったり、自分の意見を伝えるときに言葉を選んだりする力も含まれます。
つまり、話す力・聞く力・気づく力がバランスよく働くことで、円滑なやり取りが可能になるのです。
例えば、何気ない一言でも、相手の背景や立場を無視して発すると、思わぬトラブルを招くことがあります。
「お孫さんは?」と聞いたつもりでも、相手にとっては答えにくい質問だったり、内心をえぐる言葉になってしまうこともあります。
こうした無自覚な発言を減らすには、日頃から相手の価値観や状況に配慮する習慣を持つことが有効です。
また、話しすぎてしまうことにも注意が必要です。
たとえば、自分の孫の話を延々と続ける場合、それがいくら楽しい話でも、聞く側にとっては退屈や不快感に変わることもあります。
そんなときには、「私の話ばかりになってしまったけど、大丈夫?」と一言添えるだけで、印象は大きく変わります。
一方で、相手の話をよく聞く姿勢も重要です。うなずいたり相づちを打つだけでなく、相手が話しやすいように話題を広げたり、関心を持っていることを示すことで、より深い信頼関係が築けるようになります。
こうした「聞く力」は、年齢や職業に関係なく、日常の中で少しずつ磨くことが可能です。
いずれにしても、コミュニケーションは一方通行ではありません。
自分の気持ちを伝えると同時に、相手の気持ちにも丁寧に寄り添う姿勢が求められます。
そして、こうした力は意識すれば誰でも少しずつ身につけていくことができます。
日々の会話を、ただの雑談で終わらせず、相手と気持ちを通わせる機会にすることで、人間関係がぐっと豊かになっていくでしょう。
【孫自慢】うざいと思われないための会話術と話題の選び方
話が続く“聞き方”のコツや、相手に配慮した話題選びのポイントをまとめています。
自然なコミュニケーション力をさらに伸ばしたい方にぴったりです。
孫のいない人に孫の話はタブーとされる理由と配慮のポイントまとめ
記事のポイントをまとめました。
✅孫の有無を前提とした会話は相手に疎外感を与える
✅孫がいない人生も尊重されるべき生き方である
✅孫の話題は共有されにくい個人的な話に過ぎない
✅孫がいないことを「欠落」とみなす価値観が偏見を生む
✅孫の自慢話は承認欲求のあらわれであることが多い
✅聞き手が関心を示していない場合は話題を変えるべき
✅孫のいない人には家族の話題そのものがつらい場合がある
✅写真や動画を一方的に送る行為は迷惑になりやすい
✅会話の前に相手の状況や反応を読み取る配慮が必要
✅聞かれたときだけ孫の話をするのが無難なスタンスである
✅孫がいる=勝ち組という価値観は時代遅れで危うい
✅孫の話題は相手によってはハラスメントになる可能性がある
✅距離感を意識しながら会話を続けることが関係維持に有効
✅共通の関心ごとを話題にすることで円滑な会話ができる
✅思いやりあるコミュニケーション力が人間関係を深める鍵となる
最後までお読みいただきありがとうございました。


