お食い初めは、生後100日頃に赤ちゃんの健やかな成長を願って行う日本の伝統行事です。しかし現代では、家族構成や生活スタイルの多様化により「お食い初めは どちらの実家で行うべきか」と悩む人が増えています。片方の親だけを呼ぶ形にしてもよいのか、義両親との関係やお金の話をどう扱うかなど、判断が難しいポイントも多いものです。
また、「両親のみ」でお祝いする家庭も少なくありませんが、それに対して周囲からトラブルが起きないか心配になることもあります。さらに、「やらないとどうなる?」と迷ったり、「お食い初めを過ぎても大丈夫?」と時期について不安になったりする方もいるでしょう。
本記事では、そうした迷いを持つ方に向けて、お食い初めをめぐるさまざまな疑問に丁寧にお答えします。やり直せますか?という疑問や、実際に「お食い初めを しなかったら 後悔」があったかどうかなど、リアルな声や事例も交えながら解説します。
さらに、お食い初めの代わりになるものとして写真や手形などの記録方法についても紹介し、どんな状況でも気持ちを込めて赤ちゃんを祝えるヒントをお届けします。
祖父母の立場として控えめに支える姿勢や、赤ちゃんの両親の意向を尊重する関わり方についても触れていきます。家族全体が心地よく過ごせる思い出の日となるよう、ぜひ参考にしてください。
お食い初め どちらの実家で行う?
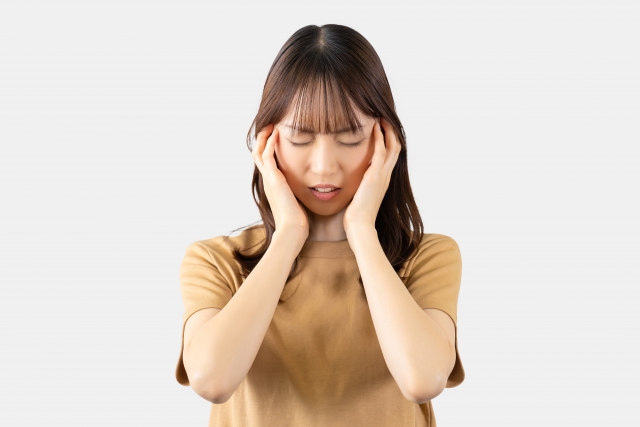
- 片方の親だけ呼ぶのは失礼なのか?
- トラブルを防ぐために大切な配慮とは
- 両親のみで行うケースの背景と意図
- 義両親 お金を出さない場合の判断基準
- やらないとどうなる?と悩んだときの考え方
片方の親だけ呼ぶのは失礼なのか?
お食い初めに「片方の親だけ」を呼ぶことについて、気を遣う方は少なくありません。呼ばれなかった親側が不満を抱いたり、家族間に微妙な空気が流れたりする可能性もあるためです。とはいえ、必ずしも両家を招待しなければならない決まりがあるわけではありません。
まず、お食い初めは法律で定められた行事ではなく、あくまで赤ちゃんの成長を願う家庭内のお祝いです。両親と赤ちゃんの意向や状況に合わせて自由に進めることができます。そのため、片方の親のみを呼ぶことが絶対に失礼というわけではありません。
例えば、実家が近く、義実家が遠方で日程調整が難しい場合や、義両親との関係性が希薄で普段から交流が少ない場合などは、実家の両親のみを呼んで行うケースも珍しくありません。特に、育児や出産に対するサポートが一方の親に偏っていた場合、「感謝の気持ちとして呼びたい」と考えるのも自然なことです。
ただし、親族間のバランスや関係を気にする人が多いのも事実です。後々の誤解やわだかまりを避けるためには、呼ばない側の親にあらかじめ一言伝えておくのが賢明でしょう。「今回は家の事情で○○側だけで行うことになりました」と丁寧に説明することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
お祝いの場は赤ちゃんを中心とした明るい時間にしたいものです。そのためにも、大人同士の配慮が大切になります。無理に形式にこだわるのではなく、各家庭の事情に寄り添った対応を心がけることが求められます。
トラブルを防ぐために大切な配慮とは

お食い初めは赤ちゃんにとって大切な節目の行事ですが、その準備や招待の仕方によっては、親族間で思わぬトラブルに発展することがあります。特に「どちらの実家を呼ぶか」「どちらが主導して行うのか」などが原因で、気まずさを感じることも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐには、まず夫婦間でしっかりと意見をすり合わせておくことが重要です。片方の実家だけを招く場合は、その理由や事情をきちんと共有し、納得したうえで判断する必要があります。相手の親に対しても、「呼ばなかったのは無視ではない」という説明を添えると、誤解を避けやすくなります。
また、義両親や実家の親に声をかける際には、形式的であっても礼儀正しく連絡を入れることが大切です。たとえ参加しないとしても、「一応報告してくれた」という事実だけで、受け取る側の印象は大きく変わります。
我が家の場合は、息子から日時と「後日写真を共有するね」と連絡があり、お祝い金を贈るに留めました。若夫婦の考えを尊重した形をとりました。
一方で、親族を巻き込まずに家族だけで静かに祝いたいという方針も、もちろん尊重されるべきです。その場合も、「今回は夫婦と赤ちゃんだけで行う予定です」と丁寧に伝えることで、後々の関係性にヒビが入るのを防げます。
さらに、金銭面や準備の分担についてもトラブルの火種になりやすいポイントです。出資者を偏らせないよう調整するか、すべて自分たちで賄うと決めてしまうことで、角が立ちにくくなります。
形式や慣習にとらわれすぎず、丁寧な説明と配慮を心がけることで、温かいお祝いの場を実現することができます。
両親のみで行うケースの背景と意図
最近では、お食い初めを「両親のみ」、つまり赤ちゃんのパパとママだけで行うご家庭が増えています。このようなスタイルが選ばれる背景には、現代ならではの家族構成や価値観の変化が関係しています。
共働き世帯や核家族が一般的になった現在、祖父母と日常的な関わりが少ない家庭も少なくありません。このため、親族を招くよりも、日ごろ赤ちゃんと過ごしている夫婦で静かに祝いたいと考えるのは自然な流れです。
また、スケジュールや距離の問題も大きな理由のひとつです。どちらかの親が遠方に住んでいる場合や、親族が高齢で移動が困難な場合は、無理に集まることを避けるケースもあります。さらに、感染症対策の観点からも、大人数で集まることを控える傾向が近年高まっています。
その他にも、義両親との関係があまり良好でない場合や、干渉を避けたいという思いから、両家を招かずに夫婦のみで完結する選択をする人もいます。誰にも気を使わず、家族のペースで祝えることが最大のメリットと言えるでしょう。
ただし、後になって「なぜ呼ばなかったのか」と聞かれることもあるため、前もって一言連絡を入れておくと安心です。「今回は小さく家族だけで行う予定です」と伝えるだけで、不要な誤解を避けることができます。
このように、「両親のみで行う」という選択は、特別な事情があるというよりも、家族の心地よさを優先した自然な流れと言えるでしょう。
義両親 お金を出さない場合の判断基準

義両親がお金を出さないからといって、お食い初めに招待すべきでないという判断を下すのは早計かもしれません。経済的支援の有無だけで招待の可否を決めてしまうと、後々の人間関係に影響を及ぼす可能性があります。
お祝い事における「お金の出し方」や「関わり方」は、家庭ごとに大きく異なります。義両親が援助をしてこない背景には、単に控えめな性格であることや、「子育ては夫婦の責任」と考えている価値観があるのかもしれません。お金を出さない代わりに、口も出さないというスタンスを貫いている場合、かえってトラブルになりにくいという見方もできます。
一方で、「なぜうちだけが負担しているのか」と不満を感じることもあるでしょう。そのようなときは、お祝いの目的を再確認することが大切です。お食い初めは誰かのための接待ではなく、赤ちゃんの健やかな成長を願う場です。親族をもてなすことが主目的になってしまうと、負担感ばかりが増してしまいます。
判断基準としては、「呼ぶか呼ばないか」をお金の有無だけでなく、普段の関わり方や赤ちゃんとの距離感を踏まえて考えることが重要です。義両親が特に関心を示さないのであれば、無理に声をかけなくてもよいという選択肢もありますし、形式的にでも招待状を送ることで礼を尽くすという方法もあります。
どちらにせよ、夫婦で十分に話し合い、納得した上で決めることがもっとも大切です。周囲に流されず、自分たちにとってストレスのない形を選ぶことが、円満な家族関係にもつながります。
やらないとどうなる?と悩んだときの考え方
「お食い初めをやらないとどうなるのか」と悩む方も多いかもしれません。結論から言えば、お食い初めをしなかったからといって、赤ちゃんの成長や健康に悪影響が出ることはありません。
お食い初めはあくまで伝統的な儀式であり、必須の行事ではないからです。実際、家庭の事情や体調、タイミングの問題から実施しなかったという家庭も少なくありません。中には、形式的な意味合いよりも、赤ちゃんとの日常の時間を大切にしたいという思いから省略する人もいます。
とはいえ、「やらなかったことで後悔するのではないか」と心配になることもあるでしょう。ここで考えてほしいのは、「何のために行うのか」という目的です。お食い初めは赤ちゃんの成長を祝う気持ちを表す場であり、必ずしも伝統的な形式にこだわる必要はありません。
例えば、当日はできなかったけれど、後日ゆっくりと記念写真を撮ったり、手形や足形を残したりするだけでも、十分に思い出になります。そうした“代わりのお祝い”を選ぶことで、気持ちの整理もしやすくなるはずです。
また、義実家や親戚の目が気になる場合は、「自分たちの判断で無理のない範囲で祝いました」と一言伝えるだけで十分です。無理に義務感から行うよりも、心を込めたシンプルなお祝いのほうが、赤ちゃんにとっても家族にとっても温かい記憶になるでしょう。
大切なのは「祝うことの形」ではなく「祝う気持ち」です。自分たちに合った方法で、その節目を丁寧に過ごすことができれば、それで十分価値のある1日になります。
お食い初め どちらの実家と祝うべきか?

- お食い初めを過ぎても大丈夫なの?
- やり直せますか?タイミングに決まりはある?
- お食い初め しなかった 後悔はある?
- お食い初め 代わりになるものの具体例
- 祖父母の立場として控えめに支える心構え
- 赤ちゃんの両親の意向を尊重する姿勢とは
お食い初めを過ぎても大丈夫なの?
お食い初めは、赤ちゃんの生後100日前後に行うとされる日本の伝統行事です。ただし、この「100日」という日数はあくまで目安であり、絶対的な期限ではありません。実際には、都合や体調に合わせて柔軟に日程を変更する家庭が増えています。
例えば、赤ちゃんやママの体調がすぐれなかったり、家族全員の予定が合わなかったりすることもあります。さらに、地域によっては110日や120日などに行う風習がある場所もあるため、多少日数を過ぎたからといって問題視されることはほとんどありません。
大切なのは、赤ちゃんの成長を家族で祝う気持ちをもつことです。日程にとらわれ過ぎて無理に計画を立ててしまうと、体力的・精神的に負担になりかねません。お祝いの準備や儀式は、赤ちゃんにとっても周囲の家族にとっても快適に進められる状態で行うことが理想的です。
また、お食い初めのタイミングを逃してしまった場合も、できるだけ早い時期に改めて日を決めれば問題ありません。「成長を祝うイベント」は遅れてしまっても、家族の思い出としてしっかり残すことができます。
お祝いごとは、完璧な日にちよりも、家族がそろい、笑顔で過ごせることが何より大切です。生後100日という節目にとらわれすぎず、赤ちゃんと向き合いながら、自分たちに合ったタイミングで祝っていきましょう。
やり直せますか?タイミングに決まりはある?
お食い初めの儀式に「やり直し」という考え方は決して珍しいことではありません。たとえ当日の段取りでうまく進まなかったとしても、後日もう一度行ってもまったく問題ありません。
そもそも、お食い初めは神事ではなく、家族の記念日として行われる行事です。そのため、形式や回数に厳密なルールは存在しません。途中で赤ちゃんが泣き出してしまったり、準備がうまく整わなかったりすることも当然あり得ます。そのようなときは、あらためて家族のスケジュールを調整し、落ち着いた日を選んで仕切り直してもよいでしょう。
例えば、「この日は食器が用意できなかった」「記念写真が撮れなかった」など、気になる点が残った場合は、その部分だけを後日補完する形で行う家庭もあります。歯固めの儀式や祝い膳の再準備はもちろん、記念撮影だけを別日に設定して、より良い記録を残すという工夫も可能です。
また、赤ちゃんにとっても一度のイベントですべてがスムーズに進むとは限りません。機嫌や体調を見ながら無理のない形で取り組むことが、結果的に家族にとっても良い思い出になります。
タイミングにこだわりすぎると、かえって気持ちに余裕がなくなることもあります。お祝いの本質は「願いを込めること」にあるため、日にちや流れが少し変わっても問題はありません。やり直すことに後ろめたさを感じる必要はなく、むしろ柔軟に進めた方が心からの思い出になるでしょう。
お食い初め しなかった 後悔はある?

お食い初めを行わなかった場合、後悔するかどうかは家庭や人によって異なります。やらなかったことで何か重大な問題が起きるわけではありませんが、「やっておけばよかった」と感じる声があるのも事実です。
後悔の多くは、「記録に残せなかった」という点に集約されます。例えば、赤ちゃんの成長アルバムを見返したとき、「この時期に何もしていなかったな」と感じて寂しくなることがあるようです。また、周囲の家庭がSNSなどで豪華な祝い膳や写真を投稿しているのを見ると、つい比較してしまう人も少なくありません。
一方で、「しなかったけれど後悔はしていない」という人もたくさんいます。その理由としては、当時は育児や体調の都合で余裕がなかったことや、無理に準備をしてストレスになるよりも、落ち着いた気持ちで赤ちゃんと向き合う時間を大切にしたいと考えたことが挙げられます。
このように言うと、どちらの選択にも意味があることがわかるはずです。形式にこだわって無理をしてしまうくらいなら、「今はできない」と決めることも立派な判断です。後悔が心配な場合は、写真を撮る、手形を残すなど、小さな記録だけでも残しておくと安心です。
思い出というのは、形そのものではなく「誰とどんな気持ちで過ごしたか」によって作られていきます。後悔を避けるためには、自分たちにとって無理のないスタイルで、赤ちゃんの成長を祝い、記録していくことが何より大切です。
お食い初め 代わりになるものの具体例
お食い初めを正式な形で行うことが難しい場合でも、代わりになるお祝いの方法はたくさんあります。むしろ最近では、伝統にこだわらず、自分たちのスタイルで祝う家庭が増えてきています。
たとえば、記念写真の撮影を行う方法があります。写真スタジオで衣装を着せて撮るだけでも、しっかりと記録に残りますし、祖父母への報告にもなります。自宅でも背景に「100日祝い」や「100days」のガーランドを飾って、簡易的なフォトブースを作れば手軽に記念の一枚が撮影できます。
また、手形や足形を残すのも人気の方法です。専用キットを使えば、安全に赤ちゃんの手足のサイズを記録できます。額に入れて飾ったり、アルバムにまとめたりすることで、成長の証として長く残すことができます。
そのほか、赤ちゃん用の離乳食ケーキを用意して、家族だけでミニパーティーを開くのも素敵な方法です。見た目が華やかになるだけでなく、上のきょうだいも一緒にお祝い気分を味わえるメリットがあります。
こういった代替方法は、準備や費用の負担を減らしながらも、赤ちゃんへの愛情をしっかりと伝えることができます。形式にとらわれすぎず、家族が笑顔で過ごせる形こそが、いちばん大切なお祝いの姿です。
ただし、何を選ぶにしても「何のために行うのか」を忘れないことが重要です。赤ちゃんの記念日であるという基本を押さえた上で、それぞれの家庭に合った方法を選んでいきましょう。
祖父母の立場として控えめに支える心構え
お食い初めをはじめとした赤ちゃんの節目行事では、祖父母がどのような立ち位置で関わるかが円滑な関係を保つうえでとても重要です。特に義理の親として参加する場合は、控えめな姿勢と柔軟な受け入れ方が求められます。
お祝いの場は赤ちゃんとその両親が主役であり、祖父母はあくまで“見守る立場”であることを意識する必要があります。過度な口出しや仕切りを行うと、主導権を握ろうとしているように受け取られ、夫婦間で不満が生まれるきっかけになることもあります。良かれと思ったアドバイスが、かえって距離を生むこともあるため注意が必要です。
ここで大切なのは、「求められたときに手を差し伸べる」という姿勢です。準備や費用についても、無理に介入せず、相談されたときだけ助けるという対応が、円満な関係を築くコツと言えるでしょう。例えば、「もし何か必要であれば遠慮なく言ってね」と一言添えるだけで、相手に安心感を与えることができます。
また、当日の振る舞いにも気配りが求められます。赤ちゃんを抱っこしたり、写真に写ったりする場面では、自分から出しゃばらず、親の意向を確認してから行動するよう心がけましょう。小さな配慮が、家族としての信頼関係を深めていく一歩になります。
行事は一度きりでも、家族の関係はこれから何年も続いていきます。だからこそ、祖父母としての控えめな立場を理解し、必要なときにそっと支える姿勢を忘れないようにしたいものです。
赤ちゃんの両親の意向を尊重する姿勢とは

お祝いごとにおいて、親族の意見が交錯する場面は珍しくありません。しかし赤ちゃんの行事においてもっとも尊重すべきなのは、赤ちゃんの両親の意向です。どのような形式で行うか、誰を招待するか、費用をどうするかといった判断は、すべてその家庭の価値観に基づいて行われるべきものです。
例えば、お食い初めの規模を小さくしたいと考える両親もいれば、できる限り伝統的な形式で行いたいと望む家庭もあります。どちらが正しいということはなく、それぞれの家庭に合ったスタイルがあるという前提を理解して接することが重要です。
このとき、祖父母や親族が自分たちの経験をもとに意見を伝えること自体は悪いことではありません。ただ、その伝え方には十分な配慮が必要です。「昔はこうだったから」「うちの時はこうした」といった一方的な言い回しではなく、「何か手伝えることがあるかな?」といった支援の姿勢を示すことが、信頼を築くポイントになります。
また、両親の意向があまり明確でない場合でも、焦って意見を押し付ける必要はありません。ときには少し時間をおいて、相手が自分のペースで決断できるよう見守ることも大切です。
お祝いの主役は赤ちゃんですが、その赤ちゃんを育てていくのは両親です。だからこそ、彼らの判断に敬意を払い、その決断を支えるという立場を保つことが、周囲にいる大人の役割ではないでしょうか。
これから先、運動会、七五三、入園・入学といった節目も続いていきます。そのたびに「親の意向を尊重する」という姿勢を貫くことで、家族としての信頼が少しずつ深まり、あたたかな関係が築かれていくはずです。
お食い初め どちらの実家で行うか迷ったときの考え方まとめ
記事のポイントをまとめました。
✅お食い初めは家庭ごとの事情に合わせて自由に決めてよい
✅片方の親だけを呼ぶこと自体はマナー違反ではない
✅呼ばない側には事前に一言伝えておくとトラブルになりにくい
✅家族間の温度差がある場合は夫婦間で意見をそろえておく
✅義両親が援助しない場合でも招待の判断は慎重にする
✅金銭的援助の有無だけで招待可否を決めないようにする
✅両親だけで行うスタイルも一般的になりつつある
✅親族を招かず家族だけで祝う選択も尊重されるべきである
✅感染症や距離の問題で集まれない場合も無理に調整しない
✅お食い初めを過ぎても祝うことに支障はない
✅形式的に失敗してもやり直しは可能である
✅儀式を省略しても写真や記録で思い出は残せる
✅行わなかった場合の後悔を防ぐには代替案を考えておく
✅祖父母は出しゃばらず求められたときに支える姿勢が望ましい
✅両親の意向を第一に尊重し、柔軟に受け入れる心構えが必要
最後までお読みいただきありがとうございました。

