孫に会う頻度は、家庭の事情や距離によって大きく異なります。近くに住んでいても毎週会えるとは限らず、遠方であれば年に数回というケースも珍しくありません。では、孫と会う頻度は平均してどのくらいなのでしょうか。また、60代で孫がいる割合は?実家に行く頻度は?といった具体的な統計を知ることで、自分の家庭との違いや共通点が見えてきます。
さらに、孫が離れて行くのはいつ頃なのか、祖父母と孫が同居している割合はどの程度なのかといった現状も気になるところです。高齢者と孫のコミュニケーションは?孫がいる確率は?といったデータを踏まえ、今後の関わり方を考えるヒントを探ります。
一方で、孫としたいことと遊びの効果を理解すれば、限られた時間でも充実した交流が可能になります。しかし、息子(娘)の孫になかなか会えない状況や、会えない期間を前向きに過ごす工夫も欠かせません。
息子(娘)夫婦との信頼関係を深める方法を知ることは、長期的に良好な関係を築くための土台となります。この記事では、これらの視点から孫との関係を多角的に見つめ、今後の交流をより豊かにするための情報をお届けします。
孫に会う頻度の現状と世代別の特徴

- 孫と会う頻度は平均してどのくらい?
- 60代で孫がいる割合は?
- 孫がいる確率は?
- 実家に行く頻度は?
- 孫が離れて行くのはいつ頃?
孫と会う頻度は平均してどのくらい?
多くの家庭では、孫と会う頻度は「月に1回」程度が最も多い傾向にあります。全国調査でも17%前後が月1回のペースで会っているという結果が出ており、次いで「2~3か月に1回」や「半年に1回」という回答が続きます。(出典:アットプレス)
つまり、近くに住んでいても毎週会える家庭は限られ、一定の間隔を空けて会うことが一般的です。
このような頻度になる背景には、現代の家族構成やライフスタイルの変化があります。例えば、共働き家庭が増えたことで子ども世代は休日も忙しく、祖父母の家に行く時間を確保しにくくなっています。また、遠方に住んでいる場合は移動時間や交通費がかかるため、年に数回しか会えないケースも少なくありません。
一方で、理想の頻度については「月に2回以上会いたい」と考える祖父母も一定数います。特に孫の成長が早い幼児期は、短期間で変化が大きく、会うたびにできることが増えているため、その瞬間を見逃したくないと感じる人が多いようです。ただし、会う回数を増やすには、双方の生活リズムや負担を考慮する必要があり、無理のないスケジュール作りが大切です。
60代で孫がいる割合は?
60代になると、半数以上が祖父母になっているという統計があります。性別で見ると、男性はおよそ50%、女性は66%前後が孫を持つ年代にあたります。さらに細かく見ると、男性では60代後半、女性では60代前半から後半にかけて孫がいる割合が増加し、特に65〜69歳の女性では7割以上が祖母になっています。(出典:第一生命経済研究所)
この数字の背景には、晩婚化・晩産化による初孫誕生の時期の後ろ倒しがあります。昭和の時代は50代で祖父母になる人が多かったのに対し、現在では60代になってから初孫が生まれるケースが一般的になっています。
また、孫の人数については平均2〜3人程度で、特に60代後半の女性は2.7人とやや多めです。ただし、4人以上の孫がいる家庭は全体の3割未満であり、少子化の影響が数字に表れています。こうしたデータは、同世代との会話や家族計画を考える際の参考になるだけでなく、孫との関わり方や生活設計を考える上でも役立ちます。
孫がいる確率は?
全体的に見ると、日本国内で孫がいる人の割合はおよそ8割に達します。これは、子どもがいる家庭の多くで、何らかのタイミングで祖父母の立場になるという現状を示しています。平均すると、一人あたりの孫の数は3.6人程度ですが、そのうち同居している孫は1人未満、別居している孫は2人以上という構成が一般的です。(出典:OKB総研)
この確率は年齢層によって大きく異なります。50代前半ではまだ孫がいない人が多数派ですが、60代に入ると割合が一気に増加します。また、地域差や家族のライフスタイルも影響し、都市部では晩婚化が進んでいるため孫ができる時期が遅く、地方では比較的早い傾向があります。
興味深いのは、孫がいる人の多くが「直接会う機会が減っても、写真やメッセージで関わりを持つ」ことを重視している点です。物理的な距離があっても、デジタルツールの活用で関係を維持できる環境が整ってきたことは、現代ならではの特徴といえるでしょう。孫がいる確率の高さは、同時に祖父母としてどのように関わるかという新たな課題とも結びついています。
実家に行く頻度は?

実家に行く頻度は、家族の生活環境や距離によって大きく異なります。全国的な傾向としては、年末年始やお盆など長期休暇に合わせて帰省する人が多く、年1〜2回というペースが最も一般的です。特に遠方に住んでいる場合は、移動時間や交通費の負担が大きく、この回数が限界になる家庭が少なくありません。
一方で、実家が比較的近距離にある場合は、月1回以上訪問する人も一定数います。徒歩や車で短時間で行ける距離であれば、週末の食事や買い物を兼ねて顔を出すなど、日常的な交流が可能です。また、子育てや家事のサポートを受けるために頻繁に実家に行く家庭もあります。
ただし、頻度の多さが必ずしも関係の良さを意味するわけではありません。無理に回数を増やすと、双方に負担がかかり、かえってストレスを感じることもあります。実家訪問は、距離や予定、家族の体調などを考慮し、お互いに気持ちよく会えるペースを見つけることが大切です。
孫が離れて行くのはいつ頃?
孫が祖父母から自然と距離を取る時期は、おおむね小学校中学年から高校入学頃までに訪れることが多いです。小学校3〜4年生頃になると、友達との遊びや習い事が生活の中心になり、祖父母宅に行く頻度が減少します。この段階では「友達と遊びたい」という気持ちが強まり、家族よりも同世代との時間を優先する傾向が見られます。
中学生になると、部活動や定期テスト、受験勉強などで忙しくなり、さらに会う機会が減ります。この頃は思春期の影響もあり、会話自体が減ることもあります。高校生になると、アルバイトや進路準備、友人関係がさらに広がり、祖父母と過ごす時間は限られたものになります。
ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、全ての孫が同じ道をたどるわけではありません。中には成長しても変わらず祖父母と交流を続ける孫もいます。また、一時的に距離ができても、大人になってから再び関係が深まるケースも多くあります。こうした時期を過ぎてもつながりを保つためには、小さい頃からの関係づくりや、離れていても連絡を取り合う習慣が大切です。
孫に会う頻度はどれくらい?工夫と関係性づくり

- 祖父母と孫が同居している割合は
- 孫としたいことと遊びの効果
- 息子の孫 会えない場合の対応
- 会えない期間を前向きに過ごす工夫
- 息子夫婦との信頼関係を深める方法
祖父母と孫が同居している割合は
全国的なデータによると、祖父母と孫が同居している割合はおよそ12.3%で、10人に1人程度にとどまります。かつては三世代同居が一般的でしたが、核家族化や生活スタイルの変化により、この割合は年々減少傾向にあります。
同居のメリットとしては、日常的に孫と顔を合わせられるため関係が深まりやすく、育児や家事のサポートがスムーズにできる点が挙げられます。また、孫にとっても祖父母から生活の知恵や文化を自然に学べる環境になります。一方で、生活リズムや価値観の違いによる摩擦、プライバシーの確保が難しいといった課題も存在します。
同居していない場合でも、近距離に住んでいれば頻繁に会うことは可能です。逆に遠距離であれば、デジタルツールを活用した交流や、長期休暇のまとまった訪問が関係維持の手段になります。いずれにしても、同居の有無にかかわらず、互いの生活を尊重しながら交流の形を工夫することが重要です。
出典:【2023年最新】祖父母と孫の関係は?どんな影響がある?子育て世帯のパパママ300人に本音をアンケート!
※本記事の記載内容は、出典データをもとに編集・加工しています。
孫としたいことと遊びの効果

孫と一緒に過ごす時間は、祖父母にとっても孫にとっても大切な思い出となります。やりたいこととして多く挙げられるのは、季節の行事や旅行、手作り料理を囲む食事会などです。例えば、お花見や夏祭りに出かける、正月におせちを一緒に作るといった活動は、行事そのものを楽しむだけでなく、文化や家族の伝統を自然に伝える機会にもなります。また、家庭菜園や釣り、工作など、自然や手仕事に触れる体験は、孫にとって新しい発見や学びを得られる場となります。
こうした活動は、精神面にも良い影響を与えます。祖父母にとっては孫の笑顔や成長を間近で感じられることが生きがいや喜びにつながり、心の活力になります。さらに、外出や軽い運動を伴う遊びは、健康維持や体力向上にも役立ちます。一方、孫にとっては祖父母との交流が情緒の安定や自己肯定感の向上に寄与します。親とは異なる視点や包容力に触れることで、安心感を得やすくなるのです。
ただし、活動内容は双方の体力や予定に合わせることが大切です。屋外で活発に動く遊びだけでなく、家の中でのボードゲームや絵本の読み聞かせなど、静かに過ごす時間も同じように価値があります。重要なのは、何をするか以上に、笑顔で共有できる時間を持つことです。その時間こそが、世代を超えて長く心に残る財産になります。
息子の孫 会えない場合の対応
息子の孫になかなか会えない状況は、祖父母にとって大きな寂しさや物足りなさを感じる原因になります。特に息子が婿入りしている、あるいは結婚後に遠方に住んでいる場合は、距離的にも心理的にも会う機会が減りやすくなります。このような状況に直面したときは、無理に会う回数を増やそうとするよりも、関係を穏やかに維持しながら、つながりを保つ方法を探すことが大切です。
まず意識したいのは、親世代(息子夫婦)の生活リズムや育児方針を尊重する姿勢です。突然の訪問や頻繁な催促は、かえって距離を広げる原因になることがあります。代わりに、事前に都合を聞いてから予定を立てる、短時間の訪問にとどめるなど、相手に負担をかけない配慮が信頼関係を保つ鍵となります。
また、会えない期間が長くなっても、デジタルツールを活用すれば関係をつなぎやすくなります。ビデオ通話や写真・動画のやり取りは、孫の成長をリアルタイムで感じられるだけでなく、孫にとっても祖父母の存在を身近に感じるきっかけになります。さらに、誕生日や行事に合わせて手紙や贈り物を送ることも、温かい気持ちを伝える有効な手段です。
こうして直接会う機会が少なくても、関わり方を工夫すれば、孫との絆は保ち続けられます。重要なのは、会う回数よりも「どう関わるか」という質を大切にし、孫が成長したときに自然と会いたいと思える関係を築くことです。
会えない期間を前向きに過ごす工夫
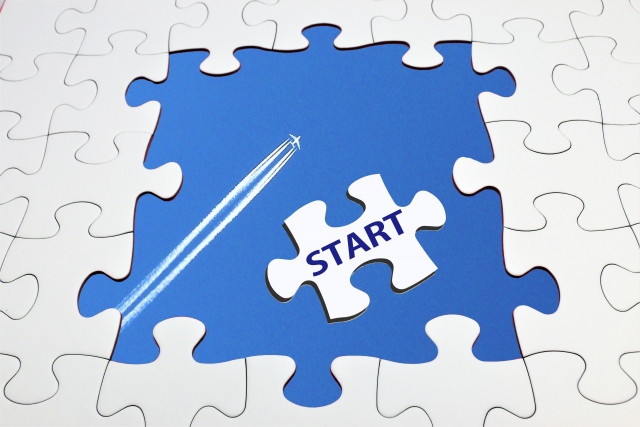
孫に会えない時間は、寂しさを感じやすい一方で、自分の生活を見直し充実させるチャンスでもあります。趣味や習い事に取り組むことで、日々に新しい刺激が生まれ、再会時の会話のきっかけにもなります。
例えば、写真や料理、ガーデニングなどを始めれば、その成果を孫に見せたり一緒に体験したりすることができ、話題の幅も広がります。
また、健康維持に努めることも大切です。適度な運動や食生活の改善を続けていれば、孫と会えたときに元気な姿を見せられます。元気な祖父母の姿は孫に安心感を与えるだけでなく、「また会いたい」という気持ちを自然に引き出します。
さらに、会えない間に孫へのプレゼントや手紙を準備しておくのも効果的です。再会したときにサプライズとして渡せば、喜びが一層大きくなります。
息子夫婦との信頼関係を深める方法

孫と会う機会は、息子夫婦との信頼関係に大きく影響されます。日頃から感謝の気持ちを素直に伝えることや、忙しい日々をねぎらう言葉をかけることは、関係を良好に保つ基本です。特に育児中の親世代は時間も心も余裕がない場合が多く、祖父母からの理解やサポートの姿勢は大きな安心材料になります。
加えて、息子夫婦の育児方針や生活スタイルを尊重することも重要です。会いたい気持ちが強くても、自分の都合だけで訪問を決めたり、子育てに口出ししすぎたりするのは避けましょう。
代わりに、「手が必要なときは声をかけてね」と伝えておくことで、相手が安心して頼れる存在になれます。こうした信頼の積み重ねが、結果として孫との交流頻度を自然に高めることにつながります。
孫に会う頻度から見る家族関係の現状まとめ
記事のポイントをまとめました。
✅孫に会う頻度は月1回が最も多い傾向
✅会う間隔は2~3か月に1回や半年に1回も一般的
✅近距離でも毎週会える家庭は少数
✅共働きや多忙な生活が会う回数減少の要因
✅遠距離では移動や費用負担が会う機会を制限
✅幼児期は祖父母がより頻繁に会いたいと感じやすい
✅60代では半数以上が孫を持つ年代
✅孫の人数は平均2~3人程度
✅孫がいる割合は全国で約8割
✅都市部は晩婚化で孫誕生が遅い傾向
✅実家訪問は年1~2回が最も多い
✅孫が祖父母から離れ始めるのは小学校中学年頃
✅祖父母と孫の同居率は約12.3%
✅孫との活動は文化伝承や情緒安定に効果がある
✅会えない場合もデジタル交流で関係維持が可能
最後までお読みいただきありがとうございました。


