「内孫外孫どっちが可愛い」と検索する方の多くは、家庭内のちょっとした違和感やモヤモヤを感じているのかもしれません。例えば、「嫁が産んだ孫は かわいくない」といった言葉にショックを受けたり、「外孫が特別に感じるのはなぜ?」と疑問を持ったりする場面もあるでしょう。内孫と外孫の違いについて、昔からの慣習や家制度の名残に触れた経験がある方も少なくありません。
一方で、現代では「内孫や外孫なんて言う言葉は古い」と感じる人も増えており、すべての孫を平等に接する祖父母の姿が好意的に受け止められるようになっています。それでも、「内孫ばかり可愛がる」態度や「内孫より外孫」といった言葉が残る場面では、どうしても心がざわつくものです。
また、お祝いごとのたびに「内孫と外孫のお祝い金の相場は?」と迷うこともあるでしょう。家族内のバランスや感情はとても繊細で、たとえ悪意がなくても些細な差が不満の火種になることもあります。
この記事では、「孫は子よりも可愛い?」という感情面の背景にも触れながら、「内孫や外孫なんて言う言葉は古い」という考え方が広がっている現代の家族像について、分かりやすく解説していきます。誰かを責めたり、優劣をつけたりするのではなく、平等に接する祖父母の姿勢がいかに微笑ましく、時代に合っているかを一緒に見つめ直してみましょう。
内孫外孫どっちが可愛いと感じる理由とは

- 内孫と外孫の違いを整理しよう
- 「内孫より外孫」とは?昔の考え方
- 「孫は子よりも可愛い」とは?
- 外孫が特別に感じられる心理的な要因
- 嫁が産んだ孫は かわいくないは本当?
内孫と外孫の違いを整理しよう
内孫と外孫という言葉は、日本の伝統的な家制度に由来するもので、孫との関係性を区別する際に用いられてきました。現在ではあまり使われない場面も増えてきましたが、親戚づきあいや冠婚葬祭の場面などでは、今でもその概念が根強く残っているケースがあります。
まず、内孫とは、祖父母の姓を継ぐ息子の子どもを指します。特に長男の子どもが該当することが多く、実家と同じ苗字である点や、祖父母と同居している場合には「内の家族」として意識されやすい傾向があります。一方で外孫は、嫁いだ娘の子どもや、別世帯で暮らす息子の子どもを指します。祖父母とは苗字が異なることが一般的で、物理的・心理的な距離が少し遠くなることも特徴です。
この区別には、古くからの「家を継ぐ」という考え方が背景にあります。家を継ぐ息子の家族=内孫は、自分たちの家系の延長線上にあるとされ、大切にされてきた歴史があります。それに対して、嫁いだ娘の家庭=外孫は、他家の一員という意識が働くため、やや距離がある存在とされてきたのです。
ただし、現代においては家制度が事実上廃止され、家族の形も多様化しています。このため、内孫・外孫という呼び方や考え方自体が古いと感じる人も少なくありません。重要なのは「孫がどちらの立場か」ではなく、「どのような関係性を築いているか」という点です。日常的に接する機会が多ければ、自然と親しみも深まりますし、距離があっても愛情をもって関われる関係も当然あるでしょう。
つまり、内孫・外孫という言葉の違いを知ることは、家族の在り方を理解する上でのヒントにはなりますが、実際の可愛がり方や関係性はそれぞれの家庭の形に委ねられています。
「内孫より外孫」とは?昔の考え方
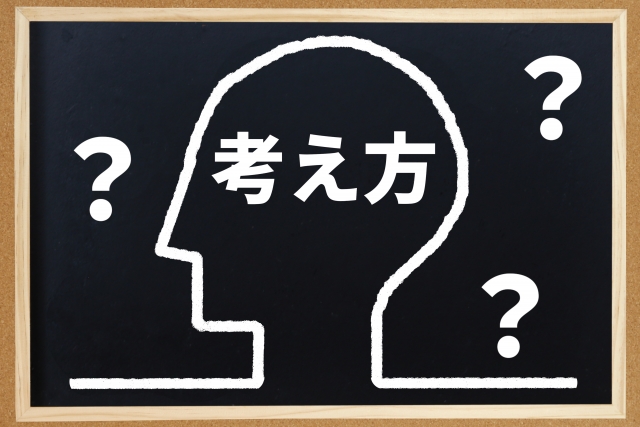
「内孫より外孫」ということわざは、祖父母にとって外孫のほうが可愛く感じられるという意味で使われます。特に昔からの日本社会では、あまり表立って語られない本音が込められている言葉のひとつです。
もともとの背景には、娘の子どもに対して祖父母が感じる「気楽さ」があるとされています。息子の子(内孫)の場合、嫁との関係性や家庭内のしきたりなどを意識する必要があり、どうしても気を遣う場面が出てきます。一方、娘の子(外孫)であれば、自分の娘との関係性がもともと近く、言いたいことも遠慮なく言えるため、より自然体で接することができるのです。
また、外孫は祖父母と同居していないケースが多く、たまに会う特別感や新鮮さが可愛さを引き立てる要因にもなります。いわゆる「たまに会うからこそ無責任に甘やかせる」という心理が働きやすいのです。これによって、普段から一緒にいる内孫よりも、外孫の方が新鮮で魅力的に映ることがあるのは、人間として自然な感情とも言えるでしょう。
しかし、現代ではこの考え方に対して疑問を抱く声も増えています。「可愛さに順位をつけるべきではない」「差別的な価値観だ」といった意見も多く、SNSや家庭内でも議論になるテーマです。孫それぞれに個性があり、それぞれに異なる可愛さがある中で、どちらが上という見方は時代にそぐわないものと感じる人も少なくありません。
このように、「内孫より外孫」という言葉は、あくまで昔の価値観に基づいたものであり、今では必ずしも当てはまるものではなくなってきました。むしろ現代では、「孫との関係性は距離よりも絆」という考え方が主流になりつつあります。
「孫は子よりも可愛い」とは?
「孫は子よりも可愛い」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。これは、日本に限らず多くの国や文化で語られる祖父母の感情を表す言葉の一つです。では、なぜ自分の子どもよりも孫の方が可愛いと感じることがあるのでしょうか。
この理由として大きいのは、「責任の有無」による心理的な違いです。親は自分の子どもに対して、しつけや教育、生活のすべてに責任を負います。しかし、祖父母は孫に対してそのような責任を直接的には持ちません。そのため、純粋に「かわいらしさ」や「癒し」の対象として孫に接することができるのです。
例えば、自分の子どもが悪さをすれば叱らなければなりませんが、孫が同じことをしても「仕方ないなあ」と笑って済ませてしまうケースもあります。これは、可愛さに対してブレーキをかける必要がない、という祖父母の立場ゆえの感情だと言えるでしょう。
さらに、祖父母にとって孫は「自分の血を受け継いだ次の世代」という実感をより強く持たせてくれる存在でもあります。成長を見ることで安心感を得られたり、人生の次のステージに意義を感じられたりすることも、孫への愛情につながっているのです。
ただし、この感情が強すぎると、親である子世代との間で価値観のズレが生まれることもあります。過干渉になったり、しつけのスタンスで口出しをしてしまったりすることは避けたいところです。
このように、「孫は子よりも可愛い」という言葉には、人生経験を積んだ祖父母が抱く深い愛情と心理的な余裕が反映されています。だからこそ、可愛がるだけでなく、親世代の気持ちを尊重しながら良い関係を築いていくことが、家族全体の絆を深める鍵となります。
外孫が特別に感じられる心理的な要因

外孫が特別に感じられる理由には、祖父母の心理や生活環境が大きく関係しています。「外孫の方が可愛い」と感じることがあるのは、単にどちらの孫かという分類だけでなく、関わり方の違いや心理的な距離が影響していると言えるでしょう。
外孫は一般的に、祖父母と同居していない場合が多く、「たまに会える存在」として特別感を持ちやすい傾向にあります。日常的に顔を合わせていると、良くも悪くも慣れが生まれますが、たまに会う孫は新鮮で、成長の変化もはっきりと感じられるため、感動や喜びがより強くなりやすいのです。これは、同じものでも「日常的にあるか」「限定的にあるか」で感じ方が変わる、いわば心理的な“希少性効果”と似ています。
また、外孫に対しては、祖父母が育児の責任を負う必要がないという点も見逃せません。しつけや教育に直接関わる場面が少ないため、厳しくする必要もなく、無条件に甘やかすことができる立場です。この「責任がないからこそ、純粋に可愛がれる」という感覚が、特別な愛情として表れやすい一因となります。
さらに、母方の外孫の場合は、祖父母にとって「自分の娘が出産した子」という点で感情移入しやすくなります。自分が育てた娘が命がけで出産し、苦労して育てている姿を身近で見ていると、その子どもにも自然と強い愛着が湧くものです。このような背景から、外孫は祖父母にとって“愛情が重なる存在”になりやすいとも言えるでしょう。
ただし、こうした感情の傾向は、すべての家庭に当てはまるものではありません。孫との関係性は、接触頻度や性格的な相性、祖父母自身の価値観によって大きく左右されます。内孫に強い愛着を持つ人もいれば、距離を置いている外孫を特に気にかける人もいます。
重要なのは、「外孫だから可愛い」「内孫だから特別」という単純な区別ではなく、それぞれの関係性の中でどう接しているかという点です。心理的な背景を理解した上で、孫それぞれの個性に寄り添った関係を築いていくことが、祖父母にとっても家族全体にとっても、より良い関係を育むポイントになるでしょう。
嫁が産んだ孫は かわいくないは本当?
「嫁が産んだ孫はかわいくない」という言葉は、一見すると非常にショッキングな表現です。しかし、これは決して孫本人に対しての嫌悪感を示すものではなく、嫁との距離感や親密度の違いが、祖父母の感情に影響を与えていることが背景にあります。
このような考え方は、嫁姑関係に課題を感じている家庭で見られる傾向があります。特に、古い価値観が残る家庭では、「嫁は他人」として線を引いてしまいがちです。すると、自然とその嫁が産んだ孫に対しても、少し距離を置いた接し方になることがあります。これは、孫に問題があるというよりも、「心の壁を乗り越えられない大人側の感情」によるものと言えるでしょう。
また、祖父母が息子夫婦との関係に気を使っている場合も見逃せません。息子の嫁に対して遠慮があると、孫に対しても思うように関わりにくくなり、感情をストレートに出しにくくなるケースがあります。特に、育児やしつけに口を出してトラブルになるのを避けたいと考える祖父母は、あえて距離を取ることで平和を保とうとするのです。
さらに、娘の子どもと比べてしまう心理も影響します。娘が産んだ孫には遠慮が少ない分だけ関わる時間が増え、自然と情が深まりやすくなります。反対に、嫁が産んだ孫には「親しみたいのに踏み込みづらい」というもどかしさが残るのかもしれません。
もちろん、すべての家庭でこのような感情が起きるわけではありません。嫁との関係が良好であれば、嫁が産んだ孫も十分に愛され、差を感じさせない接し方をしている祖父母もたくさんいます。むしろ、そうした平等な愛情が求められる現代において、「誰が産んだ孫か」ではなく、「どのように関係を築くか」が重要になっていると言えるでしょう。
このような背景を知っておくことで、誤解や不安を防ぎ、家族全体でより良い関係を築いていけるきっかけになるかもしれません。
内孫外孫どっちが可愛いかは関係ない

- 内孫ばかり可愛がる問題の実態
- 内孫 外孫と言う言葉が関係ない時代の価値観
- 内孫や外孫なんて古いと言われる理由
- 内孫と外孫のお祝い金の相場は?
- 平等に接する祖父母が増えている理由
内孫ばかり可愛がる問題の実態
「内孫ばかり可愛がる」という声は、現代の家庭においても根強く残っています。これは、家制度や跡取り文化の影響を受けてきた日本独自の感覚が背景にあると言えるでしょう。内孫とは一般的に、祖父母の家を継ぐ長男の子どもを指します。つまり、姓が同じであったり、同居していたりといった「家とのつながり」が強い立場にあるのです。
このため、祖父母にとって内孫は、家の延長線上にある存在として意識されやすく、より密接な関係が築かれがちです。日常的に顔を合わせる頻度も高いため、自然と情が深まることもあります。また、法事やお盆などの行事に一緒に参加する機会も多く、「家族の一員として一緒にいる時間が長い」という事実が、可愛がり方の差を生んでしまう要因になるのです。
しかし、このような状況が「外孫には関心が薄い」「プレゼントやお祝いに差をつけられる」といった不満につながることがあります。特に、祖父母が内孫にばかりお年玉や入学祝いを手厚く渡し、外孫には形式的なものだけ、というようなケースは、親世代のあいだで大きな不公平感を生みやすいのです。
この問題の厄介な点は、祖父母に悪気がないケースが多いということです。「一緒にいる時間が長いから自然と」「跡取りだから当然」といった感覚で行動しているため、自覚がないまま差別的な扱いになってしまっていることがあります。そのため、受け取る側が傷つきやすく、家族間の溝が広がる原因にもなりかねません。
では、どうすればこの問題を解消できるのでしょうか。一つの方法は、「差をつけない」ことを事前に家族で共有しておくことです。特に、お祝いごとやプレゼントなどは、金額や頻度をあらかじめ話し合っておくことで、誤解や不満を防ぐことができます。また、内孫・外孫問わず、会う機会を意識的に作ることも効果的です。物理的な距離を埋める努力が、心理的な距離を縮める第一歩になります。
家族関係を円滑に保つためには、無意識の偏りに気づくことがとても重要です。内孫ばかりを可愛がることが常識であった時代とは異なり、今は「すべての孫を平等に愛する」ことが求められる時代に変化しています。こうした意識の違いを理解しながら、祖父母世代と親世代で価値観をすり合わせていくことが、家族の絆をより深める鍵となるでしょう。
内孫 外孫と言う言葉が関係ない時代の価値観

現在の日本社会では、「内孫」「外孫」という言葉そのものが過去の遺物のように捉えられることが増えています。かつては家制度に基づいた「家を継ぐ」という価値観が色濃く残っており、祖父母にとっても孫との関係性に差が生じるのが当たり前とされていました。しかし、現代はそうした考え方が徐々に見直され、「内孫も外孫も関係ない」という価値観が主流になりつつあります。
この変化の背景には、家族のあり方が大きく多様化しているという事実があります。核家族化が進み、同居世帯が減少したことにより、「家を継ぐ」といった旧来の考え方は、現実的な意味を持たなくなってきました。息子の子ども(内孫)も娘の子ども(外孫)も、それぞれ別の家庭に育ち、祖父母との関係性も、同居や姓の違いに左右されなくなってきたのです。
また、情報化社会の中で、世代間の価値観の共有や意識改革が進んだことも要因のひとつです。SNSや書籍などを通じて、「平等な孫育て」や「祖父母との適切な距離感」についての考え方が広まり、家族間でもよりフラットな関係を目指す傾向が強くなっています。
さらに、現代の祖父母世代は、かつてとは異なり「孫と遊ぶことを楽しむ」存在へと変わってきました。役割や期待ではなく、純粋な人間関係として孫と関わる意識が強まり、「どちらの孫か」よりも「どんな時間を過ごせるか」が重視されるようになっているのです。
このように、「内孫か外孫か」という区別は、過去の制度や価値観に基づいたものに過ぎません。現代では、孫との距離感や関係性は多様で、血縁の深さよりも接する時間や心のつながりの方が重要視される時代となっています。これからは、孫一人ひとりの個性や成長を見守りながら、すべての孫を平等に愛する姿勢が、より自然で求められる関係となっていくでしょう。
内孫や外孫なんて古いと言われる理由
「内孫」「外孫」という言葉は、今では一部の人にとって違和感を覚える表現になりつつあります。これは、単に言葉が古くさいという意味ではなく、その背後にある考え方や価値観が、現代の家族像にそぐわなくなっているという点が関係しています。
この言葉が用いられていた背景には、かつての日本に存在した「家制度」があります。明治時代に法的に整備された家制度では、家長(多くは父親)が一家を統率し、財産や姓を息子に継がせることが当たり前でした。そのため、息子の子どもは「内孫」として家の継承者の一部と見なされ、娘の子ども(外孫)は他家の一員として、相対的に軽視される傾向があったのです。
しかし、戦後の民法改正により家制度は廃止され、家族の構成や役割は大きく変わりました。それにも関わらず、「内孫だから」「外孫だから」といった言い回しが使われ続けてきたのは、習慣としての名残に過ぎません。今の時代において、こうした考え方が依然として通用しているとしたら、それは時代遅れだと感じられても仕方のないことです。
また、現代の家庭は多様性が進んでいます。シングル家庭、再婚家庭、同性カップルによる子育てなど、従来の“標準的”な家族構成とは異なる家庭も増えています。この中で、「誰の子どもか」「どちらの姓か」にこだわること自体が、時代と逆行するものと受け止められがちです。
さらに、「内孫の方が大事にされるべき」といった発言が表に出ると、差別的な発言として批判の対象になることもあります。子どもに優劣をつける価値観そのものが、今の社会では受け入れられにくくなっているのです。
このように、「内孫・外孫」という区別が古いと言われるのは、単なる言葉の問題ではなく、社会全体の価値観が大きく変わったことの象徴とも言えます。これからの家族の在り方を考えるうえで、こうした区別に縛られず、誰もが平等に愛される関係性を築いていくことが求められています。
内孫と外孫のお祝い金の相場は?

内孫と外孫でお祝い金の額に差をつけるべきかどうかは、家族間で悩みがちなテーマのひとつです。とくに、入園・入学・成人式・結婚など、人生の節目ごとに「どのくらい包むべきか」「差をつけていいのか」といった判断が問われます。
まず、金額の目安としては、一般的な相場は以下のようになります:
- お年玉:3,000~10,000円(年齢によって変動)
- 入学祝い(小・中・高):5,000~30,000円程度
- 成人祝い:10,000~50,000円
- 結婚祝い:30,000~100,000円(関係性の深さによる)
ただし、これらの相場はあくまで参考値であり、各家庭の経済状況や、普段の付き合いの深さによって大きく変わるのが実情です。
前述の通り、昔は「内孫の方が家を継ぐ存在だから」として、多めに渡す家庭もありました。しかし、今ではそのような考え方は徐々に減少しており、「孫に差をつけるのは不公平だ」という考え方が主流になりつつあります。特に親世代は敏感で、「なぜうちの子だけ少ないのか」と不満を抱く原因になることもあるため、配慮が求められます。
それでは、どうすればよいのでしょうか。現実的な対応としては、金額は同じにしても、プレゼントの内容を少し変えるなど、バランスをとる工夫が効果的です。たとえば、内孫には現金を、外孫には同じ価値の図書カードや学用品を贈るなど、形式を変えることで、両家に対する配慮を見せることができます。
さらに、あらかじめ子どもたち(親世代)と相談しておくのも大切なステップです。金額の差が誤解を生む前に「同じにしようと思っているが問題ないか」と確認しておくことで、後々のトラブルを避けやすくなります。
お祝いは本来、孫の成長を祝う前向きな行為です。だからこそ、額の多少にとらわれるのではなく、気持ちが伝わる形を意識することが何よりも大切です。家族全員が笑顔でいられるような、思いやりのあるお祝いの仕方を選びたいものです。
平等に接する祖父母が増えている理由
近年、内孫・外孫という区別をせず、すべての孫に平等に接しようとする祖父母が明らかに増えてきました。かつては、家を継ぐ存在としての内孫を特別視し、外孫とは接し方に差が出るのが当たり前のように思われていた時代もありました。しかし、今ではそうした考え方が徐々に見直され、孫を「家系の一部」ではなく「一人の大切な存在」として見る意識が広まりつつあります。
まず、社会全体の価値観が大きく変化していることが挙げられます。家制度の名残が薄れ、家を継ぐこと自体に大きな意味を持たなくなった現代において、孫に上下や優劣をつけることは不自然に感じられるようになりました。特に都市部では、同居の有無や姓の違いに関係なく、孫は等しく愛される存在という考え方が浸透してきています。
また、祖父母世代の意識変化も見逃せません。今の60代・70代は、情報に敏感で社会の動きにも関心が高く、インターネットや書籍などを通じて「家族の平等な関係性」や「無意識の差別」について学ぶ機会が増えています。その結果、孫への接し方についても「平等であるべき」という意識を持つ人が増えているのです。
もうひとつの大きな要因は、親世代との関係性を大切にしようとする姿勢です。孫と祖父母の間に立つ親にとっては、平等に扱ってもらえるかどうかは非常に敏感な問題です。内孫だけ贔屓されれば、外孫の親は疎外感を覚えますし、その逆も同様です。そうしたトラブルを避けるために、祖父母自身が意識的に「差をつけない」努力をしている家庭も増えています。
さらに、祖父母にとって孫は、単なる「血のつながり」以上の存在になりつつあります。たとえ内孫でも、同居していなければあまり会う機会がない場合もありますし、外孫であっても頻繁に遊びに来てくれれば自然と距離が縮まります。つまり、接する機会や関係性の深さによって「可愛さ」が育まれていくという、自然な流れがあるのです。
こうして考えると、「平等に接する祖父母」が増えているのは、ただの気まぐれや理想論ではなく、社会全体の価値観の変化や、家族との関係性を良好に保とうとする実践的な行動でもあると言えます。可愛がる対象に差をつける時代は終わりを迎えつつあり、すべての孫に等しく愛情を注ごうとする姿勢こそ、現代の祖父母らしい在り方といえるのではないでしょうか。
内孫外孫どっちが可愛いかより平等な愛情が大切という考え方
記事のポイントをまとめました。
✅内孫は家を継ぐ意識が強く祖父母との距離が近くなりやすい
✅外孫は名字や世帯が異なるため心理的距離が生まれやすい
✅家制度の名残が内孫優遇の背景にある
✅昔は「内孫より外孫」の方が気楽で可愛いとされることがあった
✅外孫は同居していないため会うたびの新鮮さが魅力になる
✅娘の子どもは遠慮が少なく自然体で接しやすい
✅嫁との関係が祖父母と孫の接し方に影響を及ぼす場合がある
✅「嫁が産んだ孫は可愛くない」は関係性の築き方による
✅「孫は子よりも可愛い」は育児の責任がなく純粋に愛せるため
✅内孫ばかりを可愛がると外孫側に不満が生まれやすい
✅平等な接し方が親世代との関係にも良い影響を与える
✅今の祖父母は情報に敏感で平等意識が高まりつつある
✅「内孫・外孫」という区別は時代遅れと感じる人が多い
✅家族の多様化により内外の区別が意味を失いつつある
✅お祝い金の差はトラブルの原因になるため配慮が必要
最後までお読みいただきありがとうございました。


