お宮参りは赤ちゃんの誕生を祝い、健やかな成長を願う日本の伝統的な行事ですが、現代ではその在り方が少しずつ変わってきています。「お宮参りに祖父母を呼ばない」と検索してこの記事にたどり着いたあなたも、もしかしたら行事の進め方や親族との関わり方に悩んでいるのかもしれません。
実際、近年では「お宮参りをやらない人の割合は?」という問いが出てくるように、行事そのものを行わない家庭も増えています。特に共働きや核家族化が進む中で、「お宮参りは 家族だけで行きたい」と考える夫婦は珍しくありません。その一方で、「お宮参りに 義母が 張り切る」といったケースも見られ、祖父母との温度差に戸惑う声も聞こえてきます。
なぜお宮参りは義母が行うのですか?という疑問に代表されるように、行事の主導権や役割分担についての考え方にも世代間で違いがあります。「お宮参りは 誰が仕切る?」と迷う方がいるのも当然のことです。さらに、「お宮参りに 呼ばれなかった」と感じる祖父母の中には、関係性に傷がついてしまう例も少なくありません。
そこで本記事では、「お宮参りに 祖父母を 呼ばない」という選択に至る背景や、義母側が気を付けたい事、また角を立てずに行事に関わってもらいたいけれど、「お宮参りに義母を誘いたい?」と感じる場合はその工夫などを幅広く解説していきます。
あわせて、「お宮参りはしないといけないの?」「孫が生まれてからの行事は?」といった基本的な疑問にも触れながら、家族の気持ちを大切にしたお宮参りの形を一緒に考えていきましょう。
お宮参りで祖父母を呼ばない理由

- お宮参りをやらない人の割合は?
- なぜお宮参りは義母が行うのですか?
- 呼ばれなかった人の声
- お宮参りはしないといけないの?
- 家族だけで行きたい時
お宮参りをやらない人の割合は?
お宮参りは日本に古くから伝わる赤ちゃんの健やかな成長を祈る行事ですが、最近では「やらない」という選択をする家庭も増えてきました。現代の価値観や生活スタイルの多様化により、お宮参りの実施率は徐々に変化してきているのです。
具体的には、育児関連の調査や自治体による統計を見てみると、お宮参りを行っていない家庭は全体の2〜3割程度にのぼるといわれています。地域差や家庭環境によって差はありますが、これは決して少ない数字ではありません。
例えば、都市部では共働きの家庭が多く、平日になかなか日程を合わせられないといった理由でお宮参りを見送るケースが増えているようです。また、信仰に重きを置かない家庭では「行事そのものに意味を感じない」という声も聞かれます。
他にも、「産後すぐの移動が大変」「天候に左右されやすい」「費用がかかる」といった現実的な要因も、お宮参りをやらない理由として挙げられます。とくにコロナ禍以降、外出に不安を感じる家庭が増えたことも、実施率の低下に拍車をかけた背景の一つといえるでしょう。
このように、お宮参りをやらない家庭は一定数存在し、その背景には現代ならではの事情が見え隠れしています。行事を行うかどうかは、親としての気持ちや家族の状況によって判断されるべきであり、どちらを選んでも間違いではないのです。
なぜお宮参りは義母が行うのですか?

お宮参りと聞いて、義母が積極的に関わるイメージを持つ方は少なくないかもしれません。実際、「お宮参り=義母が仕切るもの」と感じている家庭も多く、そこに戸惑いを覚えるお嫁さんもいるようです。
本来、お宮参りの主役は赤ちゃんとその両親であり、誰が主導しなければいけないという決まりはありません。しかし、地域の風習や昔からの習慣によって、義母が中心となって準備や段取りを進めるケースが見られます。これは、伝統的に「お嫁さん側よりも夫側の家族が主催する行事」とされてきた名残といえるでしょう。
また、初孫や長男の子どもが生まれたときに、義母が「自分が動くべき」と感じる文化的背景もあります。特に地方では、「お宮参りはおばあちゃんが抱っこするもの」という風習が残っている地域もあり、その通りに行おうとする義母の姿勢が強く現れることがあります。
一方で、こうした考え方がすれ違いやトラブルの原因になることもあります。お宮参りに対する温度差がある場合、義母が張り切りすぎることで両親が戸惑ってしまうケースも見られます。とくに現代の若い世代は、プライベートな家族イベントとして簡素に済ませたいという希望を持っていることが多いため、義母の積極的な関与が負担に感じられてしまうことがあるのです。
このように、義母が関わるのは昔ながらの習慣や気遣いの一環ではありますが、価値観のズレを防ぐためには、事前にしっかりと話し合い、両家の意見をすり合わせることがとても大切です。
呼ばれなかった人の声
お宮参りに呼ばれなかったと感じる祖父母の声は、時に深いショックや悲しみを伴っています。特に、初孫や待望の孫の誕生を心から喜んでいた義父母や実父母にとって、その成長を祈る大切な行事に参加できなかったことは、寂しさを通り越して疎外感に繋がる場合もあるようです。
例えば、「孫のお宮参りを写真で知った」「日程を知らされなかった」といったエピソードは、インターネットの掲示板や口コミサイトでもたびたび話題になります。これらの声の多くは、「どうして一言相談してくれなかったのか」「自分の存在が軽んじられたように感じた」といった内容で、関係性にひびが入ることさえあるのです。
一方で、呼ばなかった側にも理由があります。「家族だけで静かに済ませたかった」「体調的に移動が大変そうだったから配慮した」「育児が大変で余裕がなかった」といった事情が語られています。このように、悪気がない選択だったにもかかわらず、祖父母側には意図が伝わらず、心のすれ違いが起きてしまうことがあるのです。
このため、お宮参りに祖父母を呼ばない場合には、事前に「今回はこういう形にする予定です」と丁寧に説明をしておくことが非常に大切です。事後報告や無言での実施は、予想以上に大きな誤解を生む原因となります。
家族間の関係を円滑に保つためにも、「なぜ呼ばないのか」「どういう意図があるのか」を言葉で丁寧に伝えることで、不要な心のすれ違いを避けることができるでしょう。
お宮参りはしないといけないの?
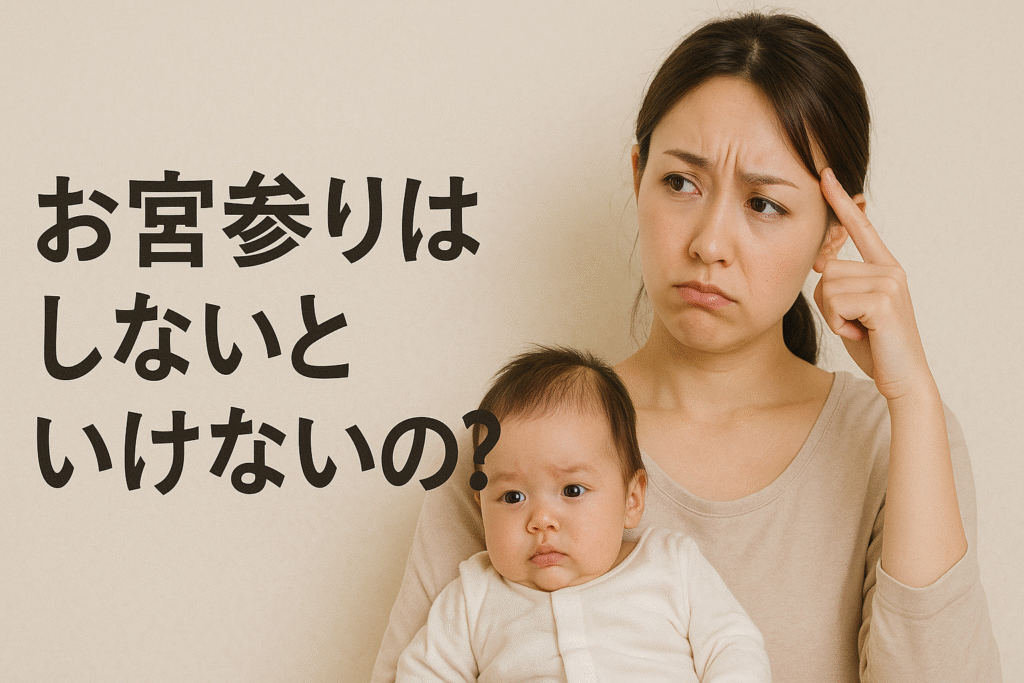
お宮参りは、赤ちゃんが生まれてから初めて神社にお参りし、健康と成長を祈願する日本の伝統行事です。とはいえ、現代において「必ずやらなければならないものか」と疑問に感じる方も少なくありません。
そもそもお宮参りは法律や義務として定められている行事ではありません。そのため、やるかどうかは各家庭の判断に委ねられており、「しない」という選択も十分に尊重されるべきです。特に、信仰や伝統に強く結びついていない現代では、形式よりも赤ちゃんや母親の体調、家族の事情を優先する傾向が強まっています。
例えば、産後間もない時期に無理をして外出することは、母体にも赤ちゃんにも負担となる可能性があります。また、暑さや寒さが厳しい季節にあたる場合、安全面から見ても実施を見送る方が良いと考える家庭もあるでしょう。行事の目的を「健康を願うこと」と捉えるのであれば、必ずしも神社でのお参りという形式にこだわる必要はありません。
一方で、祖父母世代の中には「やるのが当たり前」と感じている人も多く、その価値観の違いが家族内の摩擦を生むこともあります。そのようなときは、なぜ行わないのかを丁寧に説明することで、理解を得られる可能性が高まります。
このように、お宮参りをしないという判断は何ら非常識ではなく、家庭の状況に応じた柔軟な選択肢の一つといえるのです。
家族だけで行きたい時
お宮参りを「家族だけで静かに行いたい」と考える家庭は少なくありません。特に最近では、シンプルな形で行事を済ませたいという価値観が広がっており、親子3人で神社へ出向き、短時間で済ませるスタイルが増えています。
このような形式には、いくつかの明確なメリットがあります。まず、予定の調整がしやすく、日程変更や急な体調の変化にも柔軟に対応できます。また、授乳やおむつ替えなどが必要な新生児との外出には、少人数の方が移動や準備の負担を軽減できるという利点があります。さらに、写真撮影や参拝の進行も、自分たちのペースで行えるため、気を使わずに過ごせることが魅力です。
しかし、家族だけで行くことを選ぶ場合には、祖父母など周囲の人への配慮も必要になります。とくに、参加を期待していた義父母にとっては「呼ばれなかった」と感じてしまうかもしれません。この誤解を避けるためには、事前に「今回はこういう形で行う予定です」と伝えておくことが大切です。
単に通知するのではなく、「体調を最優先に考えたい」「最小限の外出にとどめたい」といった理由を添えることで、理解を得やすくなるでしょう。
我が家の場合は、息子から連絡がありお宮参りの後に、写真スタジオで撮影があるとの事でした。一緒にどうかと誘いがありましたが、介護があるので不参加となりました。
後日、当日の様子をミニアルバムにして贈ってくれました。
いずれにしても、お宮参りの形は家庭ごとに異なっていて当然です。家族の気持ちを優先しつつ、周囲の人にも誠実な対応を心がけることで、無理のない形で行事を進めることができます。
お宮参りに祖父母を呼ばないときの配慮

- お宮参りで義母が張り切るケースへの対処
- 義母側が気を付けたい事とは
- 義母を誘いたい?
- 誰が仕切るべきなのか
- 孫が生まれてからの行事の流れ
お宮参りで義母が張り切るケースへの対処
お宮参りを迎えるにあたって、義母が過度に張り切ることで困ってしまうという声はよく聞かれます。衣装や食事、神社の予約、写真館の手配など、すべてを主導しようとする様子にプレッシャーを感じる方も少なくありません。
義母が積極的に関与したがる背景には、「孫の成長を祝いたい」という純粋な気持ちがあります。また、昔からの風習を重んじる世代であることも関係しているでしょう。しかし、それが過剰になると、準備や雰囲気に対するズレが生じやすくなります。
このようなときに大切なのは、義母の気持ちを否定せず、冷静に「自分たちの希望するスタイル」を伝えることです。例えば、「最初の行事なので、家族だけで気軽に行いたいと思っています」や「赤ちゃんの体調に合わせて、柔軟に動きたいので簡易的にしたいです」など、相手を傷つけずに意向を伝える表現が有効です。
また、義母の気持ちを尊重しつつも「できる部分はお願いしたい」と役割を一部任せる方法もあります。例えば、記念写真の衣装選びやお祝いのお食事の手配など、負担にならない範囲で関わってもらえば、お互いに無理のない形で落ち着きやすくなります。
過度な干渉を避けつつ関係を損なわないためには、「伝え方」と「感謝の姿勢」がポイントになります。対立ではなく、協力というスタンスで向き合うことで、お宮参りが家族全員にとって心温まる思い出になるでしょう。
義母側が気を付けたい事とは
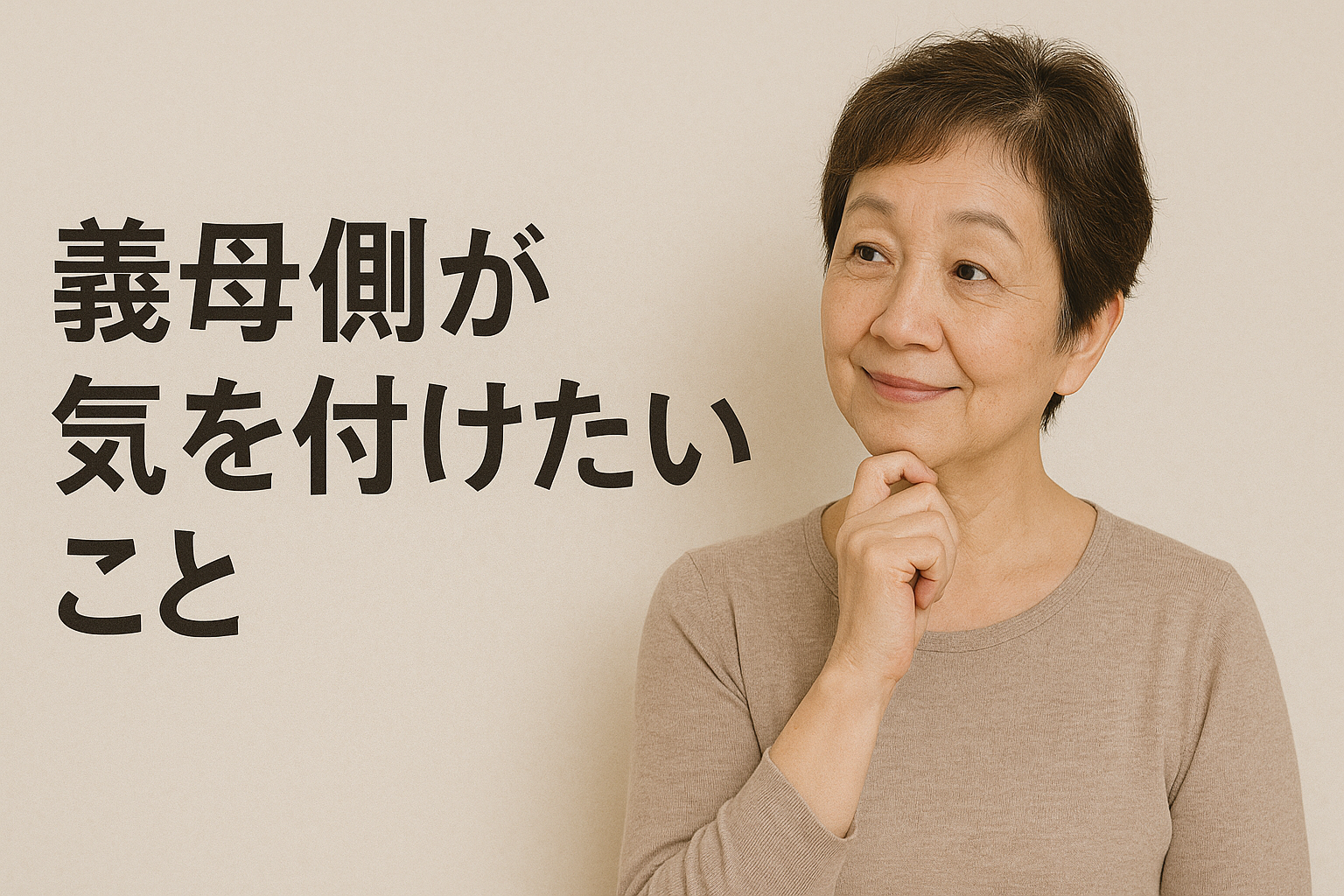
お宮参りの場面で、義母の立場にある方が気をつけるべきことはいくつかあります。赤ちゃんの誕生は家族にとって大きな喜びであり、成長を願うお宮参りは大切な節目となりますが、だからこそ行事に関わる際には「出しゃばりすぎていないか」「相手のペースを尊重できているか」を意識する必要があります。
まず大切なのは、両親の意向を尊重する姿勢です。親世代にとっては「こうあるべき」という伝統的なイメージが強く残っているかもしれませんが、現代では形式にこだわらず自由なスタイルで行う家庭も増えています。そのため、自分の価値観を押しつけず、「今回はどうしたいか」と尋ねるところから始めるのが理想的です。
また、過度な準備や提案が若い夫婦の負担になることもあります。例えば、衣装や神社の選定、記念写真の段取りなどをすべて主導しようとすると、「やりすぎでは?」と距離を置かれてしまう可能性があります。たとえ善意であっても、相手が気疲れしてしまえば本末転倒です。必要があれば「何か手伝えることがあれば声をかけてね」と一言添える程度の距離感が望ましいでしょう。
さらに、義母が気をつけたい点として、当日の服装やふるまいも挙げられます。主役は赤ちゃんと両親であることを忘れず、華美すぎる服装や場の空気を乱すような言動は避けるのが無難です。写真撮影の際も、「目立とう」とするよりは「そっと見守る」立ち位置を心がけると良い印象を残せます。
このように、お宮参りにおける義母のふるまいは、今後の家族関係にも影響を与える大事なポイントです。大切なのは、関わる気持ちは持ちつつも、一歩引いた立場でそっと支えること。気遣いと配慮のある姿勢が、家族にとっての安心感につながっていくはずです。
義母を誘いたい?
お宮参りの計画を立てる際、義母をどう誘うかで悩む方は多いようです。関係性によっては「張り切られすぎるのでは」「断られたら気まずい」と不安に感じることもあります。しかし、義母に気持ちよく参加してもらいたいのであれば、誘い方に一工夫加えることが大切です。
まず心がけたいのは、「参加を強制しない誘い方」をすることです。「ぜひ一緒に行きましょう」というストレートな表現ではなく、「もしご都合が合えば…」や「ご負担にならなければご一緒にいかがですか?」といった控えめな聞き方にすることで、相手も気を楽にして返答できます。
また、事前に全体の流れや当日のスケジュールを簡潔に伝えておくと、安心して予定を立ててもらえます。義母の立場としても、何もわからないまま声をかけられるより、どのような行事なのかを把握できた方が参加しやすくなるのです。
さらに、「○○神社でささやかにお参りする予定です」や「短時間で済ませる予定です」など、行事の規模感を明確に伝えることもポイントになります。規模が大きいと思われると、準備や服装、贈り物に悩ませてしまうことがあるからです。
声のかけ方だけでなく、「一緒に写真が撮れたらうれしいです」「赤ちゃんの晴れ姿を見ていただけたら」といった言葉を添えると、義母側も「必要とされている」と感じやすくなります。ただし、そうした表現も過剰にならないよう、あくまで自然な流れで伝えることが大切です。
義母との関係を穏やかに保ちつつ、お宮参りを気持ちよく迎えるためには、誘い方のちょっとした気配りが効果的です。形式ではなく気持ちを伝えることを意識してみましょう。
誰が仕切るべきなの?
お宮参りの準備を進める上で、「誰が主導するのが適切なのか?」という点で戸惑う方は多くいます。伝統的な行事である一方、家庭によってスタイルも考え方も異なるため、仕切り役を巡って曖昧な空気が流れてしまうことも珍しくありません。
現在では、赤ちゃんの両親が中心になって段取りを整えるケースが一般的です。お宮参りは赤ちゃんの健やかな成長を祈る行事であり、その子を育てる親が意思決定をすることが、自然な流れといえるでしょう。行く場所、日程、参加者の範囲、写真撮影の有無などを夫婦で話し合って決めていくことが基本です。
一方で、祖父母、特に義母が関与したがる場合も少なくありません。その背景には「昔は祖父母が仕切っていた」「長男の家だから主催すべき」という古い価値観が影響していることがあります。このような場合、仕切るべき人が複数現れると、準備の方向性にズレが生じたり、無用なトラブルへと発展してしまう恐れもあります。
そこで重要になるのが、「役割分担と情報共有」です。お宮参りに関しては、基本的に両親が中心となり、祖父母には協力者として関わってもらう形を取るのが無難です。たとえば、「私たちが段取りを進めるので、当日は楽しんでくださいね」といった形で、立場を明確にしながらも感謝の気持ちを伝えることで、スムーズな進行が可能になります。
誰が仕切るかで揉めるよりも、関係者が同じ方向を向いて協力し合える状態をつくることが、結果として円満なお宮参りにつながります。立場に関係なく、お互いを尊重する姿勢が何よりも大切なのです。
孫が生まれてからの行事の流れ

赤ちゃんが誕生すると、家族にとっては大きな喜びとともに、さまざまな行事が始まります。とくに私の様に初めて祖父母になる方にとっては、「どんな行事があるのか」「どのタイミングで何をすべきか」が分からず不安になることもあるでしょう。ここでは、孫が生まれてから行われる主な行事の流れを時系列でご紹介します。
まず、生後間もない時期に行われるのが命名・命名書の掲示です。出生届の提出と同時期に赤ちゃんの名前を親族や知人に知らせる意味合いで、命名書を用意し、ベビーベッドや仏壇の近くに飾る家庭もあります。形式ばらない現代では簡易的な命名カードのみで済ませることも一般的です。
その後、お七夜(しちや)と呼ばれる生後7日目の行事があります。この日は赤ちゃんの名前を披露する日とされており、親族が集まって食事を囲む風習がある地域もあります。ただし、産後の体調を最優先に考える家庭も多く、近年では省略または簡略化されることが少なくありません。
次に訪れるのが、今回のテーマでもあるお宮参りです。多くの場合、生後30日前後に神社へお参りし、赤ちゃんの健康と成長を祈願します。日数は地域や性別によって異なることもありますが、現在では両親の都合や体調を重視して柔軟に日程を調整する家庭がほとんどです。
その後、生後100日ごろに行われるのが お食い初め(百日祝い)です。この行事では「一生食べ物に困らないように」との願いを込めて、赤ちゃんに食べる真似をさせる儀式が行われます。家族でお祝い膳を囲み、記念写真を撮る家庭も多いです。特別な鯛や歯固めの石を用意する場合もありますが、最近ではレストランや写真スタジオでの開催も増えています。
そして、生後半年頃にはハーフバースデーという比較的新しい習慣が人気を集めています。正式な儀式ではありませんが、成長記録の一環として写真を残したり、家族でケーキを囲んだりと、自由なスタイルで楽しむ家庭が増えています。
最後に、生後1年の節目には 初誕生祝い(1歳の誕生日)が行われます。このタイミングで「一升餅(いっしょうもち)」を背負わせる風習がある地域もあり、「一生食べ物に困らないように」「健やかに歩めるように」と願いを込めてお祝いされます。
このように、赤ちゃんが生まれてから1年の間には、大小さまざまな行事が存在しています。ただし、すべてをきっちり行う必要はありません。家庭の考え方や体調、経済状況に合わせて無理のない形で取り入れていくことが大切です。
初孫であればなおさら、張り切りすぎてしまうこともあるかもしれませんが、行事の主役はあくまで赤ちゃんとその両親です。祖父母としては、支え手としてそっと寄り添う姿勢を心がけたいものです。そうすることで、家族全体があたたかい思い出として行事を振り返ることができるでしょう。
お宮参りで祖父母を呼ばない家庭の背景と配慮点
記事のポイントをまとめました。
✅お宮参りを行わない家庭は全体の2〜3割程度存在する
✅都市部では共働きや日程調整の難しさから実施率が下がっている
✅信仰に重きを置かない家庭では行事に意味を感じないケースがある
✅産後の体調や天候など現実的な事情で見送る家庭もある
✅義母が関与するのは伝統や地域の風習が影響している
✅義母が主導すると若い世代との温度差が生じやすい
✅お宮参りに呼ばれなかった祖父母は疎外感を感じやすい
✅家族だけでお宮参りを行う家庭が増えている
✅少人数だと日程調整や移動の負担が軽減される
✅義母が張り切りすぎたときは希望スタイルを穏やかに伝える
✅義母への役割依頼は一部に留めることで関係が円滑になる
✅義母は両親の意向を尊重し、出過ぎない姿勢が求められる
✅義母を誘う際は控えめで負担をかけない声かけが効果的
✅お宮参りの主導権は基本的に赤ちゃんの両親が持つべきである
最後までお読みいただきありがとうございました。


