「孫育てに疲れた」と感じている方は、決してあなただけではありません。いくら可愛いと思っていても、毎日のように孫の世話が続けば、ストレスや疲労が蓄積していくのは自然なことです。中には「孫の世話は したくない」と思ってしまい、罪悪感を抱える方もいるでしょう。
とくに「同居で疲れてしまう」というように生活空間を共有しているケースでは、自分の時間を持てず、気が休まらないこともあるはずです。
実際、孫が家に来るたびに「孫が来ると 疲れる」と感じる祖父母は多く、無理を続けるうちに気分が沈み、「孫ブルー」と呼ばれる状態に陥ることもあります。では、こうした疲れを感じたとき、どのように対策をすれば良いのでしょうか。日々の中でできるちょっとした工夫が、心身の余裕を取り戻す鍵になるかもしれません。
また、「孫の世話は 何歳まで続けるべき?」「60代で孫がいる割合は?」など、周囲の状況や一般的な目安も気になるところです。無理をせず、自分らしい関わり方を見つけることが、家族との良好な関係を保つための第一歩です。
この記事では、孫育てに疲れを感じている方へ向けて、背景や原因、現実的な対策までをやさしく解説していきます。心が少しでも軽くなるヒントを見つけてもらえることを願っています。
祖母初心者のわたしも決して部外者ではありません。。。
孫育てが疲れたと感じるのは普通のこと

- 孫の世話 ストレスを抱えやすい背景とは
- 孫の世話 したくないと思うのは甘えじゃない
- 孫疲れ 同居がもたらす見えない負担
- 毎日続くと限界がくる
- 何歳まで関わるべき?
孫の世話 ストレスを抱えやすい背景とは
いくら可愛い孫であっても、長時間または高頻度で関わる状況が続けば、精神的な疲れが蓄積しやすくなります。特にシニア世代にとっては、若い頃とは異なり、体力や集中力の限界が見えやすくなっているため、無理が重なるとストレスにつながるのは当然のことです。
その背景にはいくつかの要因があります。まず挙げられるのが「育児の再来」という現実です。本来なら子育てが終わり、自分の時間を楽しむはずの時期に、もう一度幼い子どもと向き合う日々が始まるのは、心理的なギャップが大きくなります。
また、現代の共働き家庭が多い社会では、祖父母に頼らざるを得ない状況が広がっています。特に保育施設の定員オーバーや、急な発熱などによる呼び出し対応など、突発的な対応を求められることも多く、日常生活の予定が立てにくくなることも精神的負担になります。
さらに、子ども夫婦との育児方針の違いがストレスになるケースも少なくありません。昔の常識が通じない現代育児では、口出しがトラブルの火種になりやすいため、発言を控える傾向が強く、結果として「言いたいことも言えない状況」がストレスを助長します。
こうした背景から、孫の世話は単なる「手伝い」ではなく、大きな責任と気疲れを伴う存在になっているのです。孫と過ごす時間が負担にならないようにするためには、無理をせず、自分の体力と気持ちに正直であることが大切です。
孫の世話 したくないと思うのは甘えじゃない
「孫の世話をしたくない」と感じることに、罪悪感を持つ必要はありません。多くの祖父母世代がそう感じるのは、ごく自然なことです。何より、その気持ちは甘えではなく、正直な心の声として大切に受け止めるべきです。
一見すると、家族のために貢献していないように感じるかもしれません。しかし、孫の世話を担うことは、想像以上に体力も気力も消耗する重労働です。ご自身の健康や生活リズムを犠牲にしてまで無理をしてしまえば、心身ともに疲弊し、最終的には孫や子どもたちとの関係にも悪影響が出る可能性があります。
また、現代のシニア世代は「老後=のんびり」ではなく、趣味や仕事、ボランティア活動など、自分らしく過ごす選択肢が多い時代です。その中で、「自分の時間を大切にしたい」という思いを持つのは当然のことであり、子育ての責任からすでに解放された立場として尊重されるべきです。
一方で、家族の期待に応えようと無理をし続けてしまうと、ストレスや疲れが蓄積し、いわゆる「孫ブルー」と呼ばれる状態に陥るリスクもあります。そうなってしまえば、孫を愛おしいと思う気持ちすら薄れかねません。
このように考えると、「世話をしたくない」と思う気持ちは、自分を守るための大切なサインとも言えます。
遠慮せず、無理せず、出来る範囲で関わるという姿勢こそ、結果として家族全体の幸せにつながるのではないでしょうか。
孫疲れ 同居がもたらす見えない負担

同居による孫育ては、想像以上に大きな負担をもたらします。表面上は「家族の協力」であっても、実際には祖父母側に家事・育児の役割が集中しがちで、知らぬ間に心身のバランスを崩してしまうケースも少なくありません。
特に問題となるのが、生活空間を常に共有していることによる「気の休まらなさ」です。自分のペースで過ごす時間や、静かな空間が確保しづらくなることで、慢性的な疲れやストレスが蓄積されやすくなります。
加えて、親子3世代が同じ屋根の下で暮らすことで、教育方針や生活スタイルの違いが顕著になります。例えば、孫のしつけを巡って意見が合わなかったり、祖父母の家事スタイルを「古い」と否定されたりすることで、孤独感や無力感に悩まされることもあるのです。
さらに、同居家庭では「祖父母は常に手伝える存在」として見られがちです。これがエスカレートすると、突発的な保育代わりやお迎えなど、予定外のサポートが当たり前になってしまい、祖父母の健康や予定が二の次に扱われてしまう傾向があります。
一方で、同居は物理的距離が近いため、断りにくいという心理的プレッシャーもあります。「疲れていても言い出せない」「やって当然と思われている」という思いが、次第に心の重荷となっていくのです。
このように、同居による孫育ては、外からは見えにくい負担が多くあります。大切なのは、祖父母の立場でも自分の意思をきちんと伝えることです。できないことは無理に引き受けず、家族全体で役割を見直す機会をつくることで、より良い関係性を築くことができるでしょう。
毎日続くと限界がくる
どれだけ孫が可愛くても、毎日その世話が続くと限界を感じるのは当然のことです。特に祖父母世代は、かつて子育てを終え、やっと自由な時間が持てるようになった段階であり、その生活リズムを根底から崩すような日常は、大きな負担になりかねません。
毎日の孫の世話には、体力だけでなく、気力や時間も必要です。学校や保育園の送り迎え、食事の準備、遊び相手、さらに宿題を見たりと、親とほぼ同じような負担がのしかかります。こうした生活が長期間続けば、誰でも疲れ果ててしまいますね。
また、毎日孫と関わる中で、叱る場面や言い聞かせる場面が増えていくと、感情面でも摩耗します。親と違って遠慮しがちな立場の祖父母は、思うように接することができず、「どうしたらいいのか分からない」と不安に感じてしまうこともあります。
さらに、同居していなくても、連日の通い育児という形で孫の世話に関わっている場合、交通費や外食費など、経済的負担も重くなりがちです。体力・気力・経済面のいずれかが限界を迎えたとき、心のバランスを崩してしまう人も少なくありません。
だからこそ、毎日の世話を当然と受け入れてしまうのではなく、週に何日まで、何時間まで、という「自分なりのルール」を決めておくことが大切です。無理をしない範囲で関わる姿勢が、長期的に良好な家族関係を保つための秘訣となります。
何歳まで関わるべき?

孫の世話に「何歳まで」という明確な決まりはありませんが、関わり方には節目を設けておくことが望ましいと考えられます。祖父母の年齢や健康状態、生活スタイルによっても異なりますが、無理のない範囲でサポートを続けることが大切です。
一つの目安として、小学校入学前の乳幼児期までは、比較的サポートが求められやすい時期です。保育園や幼稚園の送迎、病気時の看病など、親の助けが必要な場面も多く、祖父母の手を借りる機会も多くなります。しかし、小学校に入る頃から、基本的な生活スキルや社会性が育ってくるため、少しずつサポートの役割を手放すタイミングがやってきます。
例えば、学校の登下校を自分でこなせるようになったら、送り迎えは卒業する。宿題のサポートも様子を見ながら徐々に減らしていく。このように、孫の成長に応じて役割を段階的に縮小することで、負担を最小限に抑えることができます。
一方で、関わりすぎると「親の代わり」になってしまい、孫自身の自立心や親子関係に悪影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。あくまで“サポート役”としての関わりに留めることが、祖父母にも孫にも良い距離感を保つポイントです。
また、祖父母自身が「これ以上の関わりは体力的に厳しい」と感じた時が一つの区切りとなるでしょう。体調を崩してからではなく、無理を感じ始めたタイミングで子ども夫婦と話し合い、役割分担を見直すことが重要です。
孫育てに疲れた人への現実的な対策とは
- 孫が来ると 疲れる…その理由と解決策
- 「孫ブルー」とはどういう意味ですか?
- 60代で孫がいる割合は?現実を知る
- 孫に疲れた時の対策は?無理しない選択肢
- 孫との関係が人生の充実感を深めるきっかけに
孫が来ると 疲れる…その理由と解決策
孫が家に来ると嬉しい反面、どっと疲れが出るという声は少なくありません。その背景には、見えにくい心理的・身体的な負担が存在しています。
まず、子ども特有のエネルギーに付き合うこと自体が、高齢者にとっては相当の体力を要します。走り回る、騒ぐ、おもちゃを散らかす、同じ遊びを繰り返し求められる……こうした行動に数時間付き合うだけでも、ぐったりするのは無理のないことです。
また、気を使いすぎてしまうことも疲労の原因です。例えば「アレルギーはないか」「スマホはどこまで使わせていいのか」「親の教育方針に沿っているか」など、細かなことに気を配ることで、精神的に消耗します。孫の機嫌を取ろうとするあまり、思い通りにいかないときのストレスも積もりやすくなります。
こうした状況に対しては、無理をせず、いくつかの工夫を取り入れることが有効です。例えば、訪問時間や滞在時間にあらかじめ制限を設けておくことで、自分の生活リズムを守ることができます。また、家事や食事の準備など、疲れる部分は外食やお惣菜を活用するなどして「手を抜く勇気」を持つことも大切です。
さらに、子ども夫婦と事前に話し合いをしておくことで、「何をどこまでサポートするか」の線引きを共有しておくと安心です。祖父母が無理なく過ごせる環境を整えることは、結果として孫にもより良い時間を提供することにつながります。
孫が来るたびに疲れ切ってしまうようでは、本来の“楽しいふれあい”がストレスの時間に変わってしまいます。気兼ねなくリフレッシュできる工夫を取り入れながら、無理のない距離感を保つことが重要です。
「孫ブルー」とはどういう意味ですか?
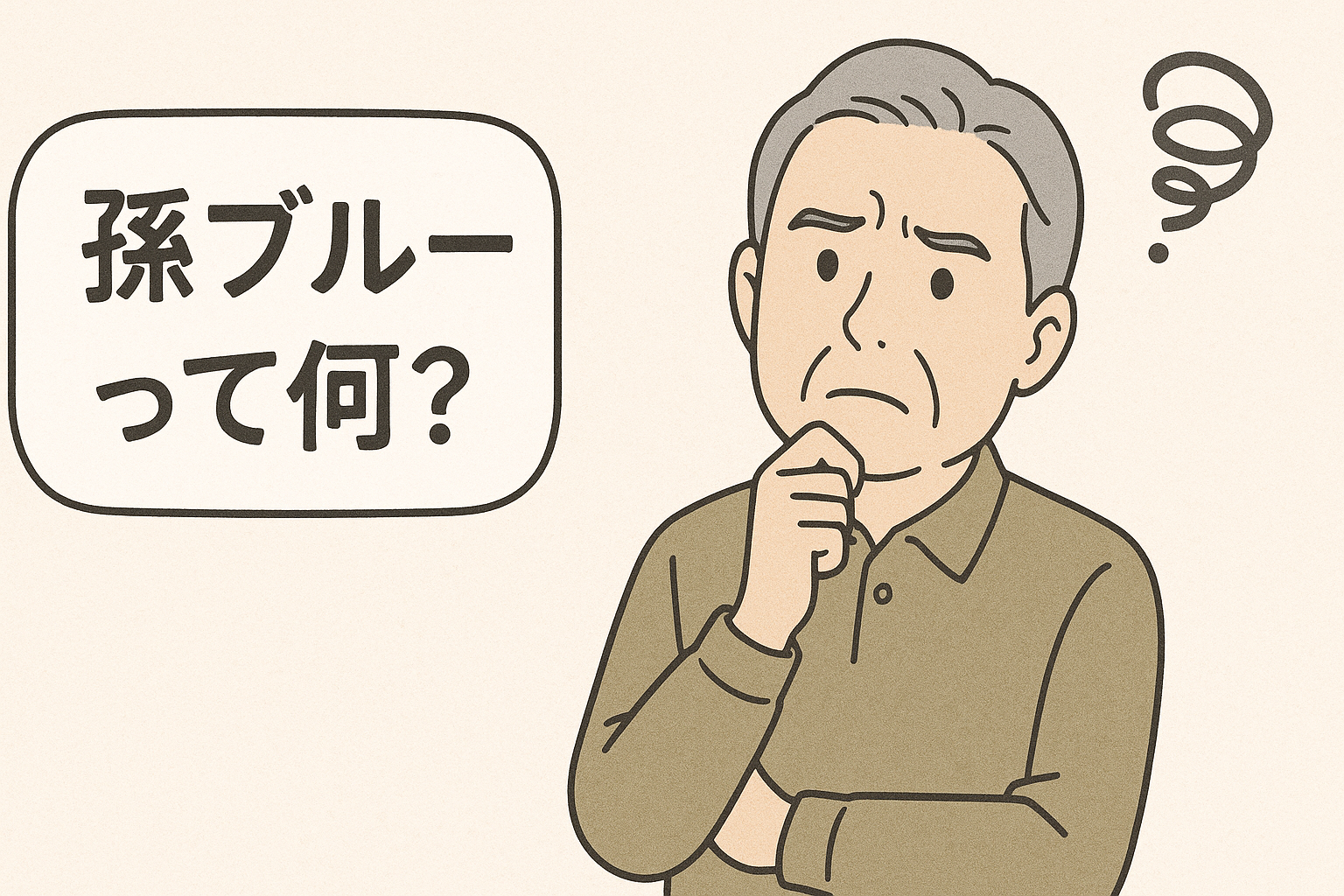
「孫ブルー」とは、孫の世話をする中で心身ともに疲れ切ってしまい、孫に会うことすら憂うつに感じる心理状態を指す言葉です。近年では、特に共働き家庭の増加によって祖父母が育児の担い手として期待される場面が増え、このような感情を抱える人が少なくありません。
一見すると、孫と過ごす時間は幸せなものであり、「かわいいから疲れるはずがない」と思われがちです。しかし、現実には、日常的に子どもを預かることになると、肉体的な疲労だけでなく、心理的なプレッシャーも大きくのしかかります。
例えば、孫の生活リズムに合わせるために自分の予定を犠牲にしたり、子ども夫婦の教育方針に合わせようと気を張り続けたりすることで、じわじわとストレスが蓄積されていきます。
このような状態が続くと、「本当は休みたい」「今日は関わりたくない」と思ってしまうことがあり、それがさらに「そんなことを思ってはいけない」という自己否定に変わることで、より深い精神的疲労を招くのです。結果的に、孫の笑顔を見ることすら楽しめなくなり、気持ちが沈んだ状態、いわゆる「孫ブルー」へと発展します。
こうした状況を未然に防ぐには、無理のない範囲で孫と接すること、そして素直な気持ちを子ども夫婦に伝えることが重要です。
「世話をするのが苦痛に感じる」という感情を抱くこと自体は、決して異常ではありません。それに気づき、心のサインを見逃さないことが、健康的な家族関係を維持するための第一歩になります。
60代で孫がいる割合は?現実を知る
60代になると、「そろそろ孫ができてもおかしくない」という感覚を持つ方も多いかもしれません。
- 男性(60代)
→ 子どもがいる方のうち、約50.5%が孫がいる祖父にあたります 。 - 女性(60代)
→ 同じく子どもがいる女性のうち、66.5%が孫をもつ祖母です 。
孫は健康づくりのモチベーションになるのか(引用元:株式会社 第一生命経済研究所)
※この割合は「子どもがいる60代に限った調査結果」であり、60代全体を対象にする事とは異なり、「孫を持つ60代男性の割合」は約半数、「女性」は約2/3という傾向です。
このように、多くの人が60代で祖父母になる中で、家族や周囲からの期待も自然と高まっていきます。「孫ができたら遊びに連れていきたい」「習い事を見守ってあげたい」など、理想の関わり方を思い描いている人も少なくありません。
しかし一方で、現代は晩婚・晩産化が進んでいることから、実際に孫ができるタイミングは人によって大きく異なります。60代になってもまだ子どもが独身であったり、育児の中心を担う世代として関わることになるなど、ライフスタイルが多様化しているのが現状です。
また、孫の有無だけでなく、その関わり方にも幅があります。例えば、近居や同居によって頻繁に世話をしている家庭もあれば、遠方に住んでいて年に数回しか会わないというケースもあります。したがって、「60代だから孫がいる」「祖父母だから育児を支援すべき」といった固定観念に縛られる必要はありません。
このように考えると、60代で孫を持つことは珍しくないものの、その関係性や役割は家庭ごとに大きく異なります。周囲と比較するのではなく、自分と家族にとって最適な関係性を築いていくことが大切です。
孫に疲れた時の対策は?無理しない選択肢

孫に疲れたと感じたとき、「こんなことを思ってはいけない」と自分を責めてしまう方は少なくありません。しかし、その気持ちは多くの人が抱えているものであり、決して否定すべきものではありません。むしろ、その感情を無視せず、どう対処していくかが重要です。
最初の対策として考えたいのは、「預かる頻度や時間を見直すこと」です。毎日のように世話をしている状況であれば、週に何日までにするか、午前中だけにするかといったルールを家族と共有することで、身体的・精神的な余裕が生まれます。
また、「すべて自分でやらなければならない」という思い込みも、疲労の原因になりやすいものです。食事の準備や送り迎えなど、負担が大きい部分は家族や外部サービスの力を借りることも大切です。最近では、シニア向けの食事宅配や子育て支援のサポートも充実してきており、無理のない範囲で利用することが可能です。
さらに、「言いづらいけれど苦しいこと」を率直に伝えることも有効です。子ども夫婦に対して、何がつらいのか、どこまでならできるのかを明確に伝えることで、無理な依頼が減り、互いの信頼関係が深まるきっかけにもなります。
そしてもう一つの選択肢として、「自分の時間を確保すること」も忘れてはいけません。趣味を楽しんだり、友人と過ごしたり、少しの間でも自分を大切にする時間を持つことで、気持ちがリセットされ、孫との関係にも良い影響を与えるはずです。
このように、「孫に疲れた」と感じた時には、我慢せず、その気持ちに正直になること。そして、無理せず選択肢を持ち、ゆとりある接し方を選ぶことが、長く良い関係を保つための大切なステップになります。
孫との関係が人生の充実感を深めるきっかけに
年齢を重ねていく中で、「何のために毎日を過ごすのか」とふと立ち止まる瞬間は誰にでも訪れます。そのようなとき、孫の存在が新たな意味を与えてくれることがあります。単に可愛い存在というだけでなく、孫との関係が、自分のこれまでの人生の延長線上にある「役割」や「つながり」を実感させてくれるからです。
たとえば、過去に自分が子育てをした経験を活かして、孫と一緒に遊んだり、世話をしたりする中で、「自分がまだ家族に必要とされている」と感じる場面も出てきます。その気持ちは、社会との接点が少なくなりがちな高齢期において、大きな心の支えになることがあります。
また、孫は価値観や日常のスピード感が全く異なる存在でもあります。そんな孫と過ごすことで、新しい発見があったり、世代を超えた学びが生まれたりすることもあります。特にデジタル機器や学校教育、流行などに触れる機会が増えると、自然と自分の視野が広がっていくのを感じるかもしれません。
ただし、関わりすぎたり、無理をしてしまえば、それは心身への負担につながります。あくまで“支える存在”であり、すべてを担おうとしないことが大切です。自分の生活リズムを大切にしつつ、無理のない距離感で孫と関わることで、日々の充実感は確実に深まっていきます。
孫との関係は、自分の人生を振り返りながら、未来を見つめる貴重な機会でもあります。それは、穏やかな日常のなかにある「意味のある時間」と言えるのではないでしょうか。
孫育てが疲れたと感じた人が知っておきたい15の視点
記事のポイントをまとめました。
✅孫の世話は長時間や高頻度になるとストレスを抱えやすい
✅体力や集中力の低下によりシニア世代は疲れを感じやすい
✅育児の再来という心理的ギャップが負担を生む
✅共働き家庭の増加が祖父母への負担を増やしている
✅育児方針の違いがストレスや気疲れにつながる
✅孫の世話をしたくない気持ちは自然なものである
✅現代のシニアは自分の時間を大切にしたいと感じている
✅無理な世話は家族関係を悪化させるリスクがある
✅同居は生活空間の共有による慢性的な疲労を招く
✅世代間の価値観の違いが孤独感の原因になりやすい
✅同居では予定外の育児負担が日常化しやすい
✅孫の世話は毎日続くと心身ともに限界を迎える
✅成長に応じて関わり方を段階的に見直すことが重要
✅孫との接し方にルールを設けることで負担を軽減できる
✅孫との関係は、未来を見つめる「意味のある時間」
最後までお読みいただきありがとうございました。

