孫の七五三に呼ばれない状況に戸惑ったり、喪中の時の孫の七五三での振る舞いに悩んだりする方は少なくありません。
七五三は誰と祝うかは家族ごとに考え方が異なり、事情によっては祖父母が招かれないこともあります。そんな時は、まず落ち着くための3つの視点を知っておくと、感情的にならず冷静な対応がしやすくなります。
また、実家か義実家のどちらか片方だけ参加するケースもあることでしょう。希望が叶わなくともメッセージカードやプレゼントで気持ちを伝える方法も有効です。
また、七五三のお祝い金の相場や渡し方や、意外と疑問に持ちやすい喪中の時の孫の七五三で配慮すべき点、喪中で七五三を控える場合の代替案を事前に理解しておくことで、迷いを減らせます。
祖父母が控えめに関わることの利点を踏まえ、孫の成長を祝う気持ちは形を変えても十分に伝わるという視点で、心穏やかに最適な選択を整えましょう。
- 呼ばれないときの受け止め方と連絡の仕方
- 実家か義実家のどちらか片方だけ参加するケースのマナー
- メッセージカードやお祝い金など控えめな祝い方の具体策
- 喪中の配慮と代替案の立て方
孫の七五三 呼ばれない時の考え方と対応

- 七五三は誰と祝う?家族ごとの考え方の違い
- 孫の七五三に呼ばれなかった時、まず落ち着くための3つの視点
- 実家か義実家のどちらか片方だけの招待になる場合
- 参列できなかった祖父母へのプレゼントの贈り方
- お祝い金 相場と渡し方のマナー
七五三は誰と祝う?家族ごとの考え方の違い
七五三は、日本の伝統的な年中行事であり、子どもの健やかな成長と長寿を祈願する儀式です。起源は室町時代や江戸時代にさかのぼり、当初は武家や裕福な商家の間で広まり、その後一般庶民にも広がったとされています。
現代においては、必ずしも伝統的な形を踏襲する必要はなく、家族ごとのライフスタイルや価値観によって祝い方が大きく異なります。
都市部の核家族世帯では、両親と子どもだけで参拝し、食事や写真撮影を短時間で済ませるケースが増えています。背景には、共働きによるスケジュール調整の困難さや、祖父母が遠方に住んでいる場合の移動負担の大きさが挙げられます。
一方、地方や近居の家族では、両家の祖父母や親戚を招いて盛大に祝う慣習が根強く残っています。
どちらが正しいという明確な基準はなく、主催するのはあくまで子どもの親です。総務省統計局の家族構成に関する調査(出典:総務省統計局「国勢調査」)によれば、核家族世帯の割合は全国で約60%に達しており、こうした家族形態の変化が七五三の祝い方にも影響を与えていると考えられます。
祖父母としては、「孫の七五三に呼ばれない」ことを単純に疎遠と受け取るのではなく、家族の事情やその年ごとの優先事項(体調、距離、予算、子どもの負担など)を理解する姿勢が大切です。
祝い方は固定されたものではなく、その時々の状況に応じて柔軟に決まるものだと認識することで、不要な誤解や心のわだかまりを避けられます。
孫の七五三に呼ばれなかった時、まず落ち着くための3つの視点
孫の七五三に呼ばれなかったと知った時、寂しさや戸惑いの感情が湧くのは自然なことです。しかし、感情だけで行動してしまうと、家族関係に思わぬ溝を作ってしまうことがあります。そこで意識したいのが、状況の確認・気持ちの整理・今後の対応という3つの視点です。
状況の確認
まずは事実を丁寧に確認します。例えば、家族だけで簡素に行う予定だったのか、祖父母の体調や距離への配慮が理由だったのか、単純な連絡漏れなのかを知ることは重要です。
情報が不足している段階で感情的な言葉を投げかけると、誤解が深まるおそれがあります。誰がどのように決定したのかを把握すれば、対応すべき相手や伝え方が明確になります。
気持ちの整理
自分の中にある寂しさや残念な気持ちを否定せず、まずは自覚することが大切です。感情を認めた上で「会えなくて寂しい」という思いを言葉にできると、相手を責めない穏やかな表現に置き換えやすくなります。これは家族間のコミュニケーションを円滑にするうえで非常に効果的です。
今後の対応
日程や方針がすでに決まっている場合、無理に干渉するのではなく、控えめに祝意を伝える方法へ切り替えます。
例えば、後日プレゼントを贈る、短いメッセージカードを送るなどの方法です。また、次回の行事に向けて連絡方法や期待する関わり方を事前に共有しておくことで、同じようなすれ違いを防げます。
この3つの視点を持つことで、感情に振り回されず、関係を損なわずに思いを届ける行動がとりやすくなります。
実家か義実家のどちらか片方だけの招待になる場合
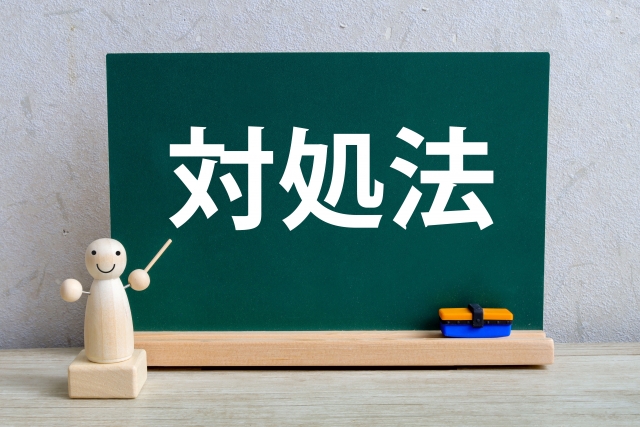
七五三で実家か義実家のどちらか片方だけの招待になるケースは珍しくありません。その背景には、物理的な距離や健康状態、日程の都合、家族間の配慮などの現実的な要因があります。こうした場合に重要なのは、若夫婦が取るべき非招待側への事前連絡と事後報告です。
事前連絡では、参加可否の確認を双方に同じ温度感で行い、参加できない側には「今回は移動負担を考えてこの形にしました」など理由と配慮を添えて説明します。これにより、受け取る側の納得感が高まり、不要な誤解を避けられます。
当日は、集合写真や動画を共有し、後日に改めて顔合わせの機会を提案することも効果的です。特に高齢の祖父母にとって、写真や映像は行事に参加した実感を得る貴重な手段となります。写真共有にはプリントやデータ送信のほか、フォトブックの作成もおすすめです。
服装や費用負担については、主催する家族の方針に従うのが無難です。過度に主導権を取ろうとすると、親世代の意向とぶつかる可能性があります。配慮を優先した対応が、長期的に見ても家族関係を良好に保つ鍵となります。
参列できなかった祖父母へのプレゼントの贈り方
祖父母が当日に参列できない場合でも、若夫婦は写真を通じて思いを伝えることは十分可能です。特に祖父母にとって、孫の成長が映し出された写真は非常に価値のある贈り物となります。形式や媒体の選び方にはいくつかのポイントがあります。
まず、贈る形式としては以下のような選択肢が考えられます。
贈る際の写真の選び方も重要です。主役である子どものソロショットに加え、家族全員での集合写真を組み合わせることで、当日の雰囲気や家族の絆をより鮮明に伝えられます。また、撮影日や簡単なメッセージ、差出人名を添えると、贈り物としての完成度が高まります。
さらに、遠方への贈り物の場合は、到着日を事前に知らせ、開封のタイミングに合わせてビデオ通話を行うのも良い方法です。こうすることで、まるでその場に一緒にいたような一体感を共有できます。
保存面を考慮し、紙媒体とデータ形式の両方を用意することも推奨されます。紙は物理的な存在感があり、データはバックアップとして機能します。この二本立ては、長期的に孫の成長記録を保管する上で非常に有効です。
お祝い金の相場と渡し方のマナー
お祝い金は地域差や家族の慣習が大きく、絶対の正解はありません。一般的な目安として紹介されるのは以下のとおりです。状況に応じて無理のない範囲で検討します。(出典:全日本冠婚葬祭互助協会調査)
| ケース | 目安とされる金額帯 | ポイント |
|---|---|---|
| 祖父母から孫へ | 1万〜5万円がよく取り上げられる | プレゼントや撮影費用を別途負担するなら低めでも十分 |
| 親族・親戚 | 5千円〜1万円程度の例が多い | 兄弟姉妹など近しい関係はやや増額もあり得る |
| 兄弟姉妹で同時祝い | 各人分を個別に包む | 一人ずつ同額がわかりやすい |
お祝い金はのし袋に入れます。紅白蝶結びの水引を用い、上段には「七五三御祝」、下段には差出人名を記します。お札は新札を用意し、表書きは筆または筆ペンで書くと丁寧な印象になります。
渡すタイミングは参拝の前後どちらでも問題ありませんが、当日が慌ただしい場合は事前または後日に写真と一緒に届ける方法もあります。
お返しについては、祖父母間では食事会や記念写真の贈呈が実質的なお礼になることが多く、金銭的なお返しは負担感を与える可能性があります。お菓子や写真といった気持ちが伝わる範囲に留めることが望ましいでしょう。
喪中時の七五三の過ごし方と祝い方

- 喪中時の七五三で配慮すべきこと
- 喪中で七五三を控える場合の代替案
- 祖父母が控えめに関わることのメリット
- 孫の成長を祝う気持ちは、形を変えても伝わる
- 七五三に呼ばれない時や喪中時での配慮と心の持ち方
喪中時の七五三で配慮すべきこと
喪中は故人をしのぶ期間であり、行事の扱いに迷いが生じやすい時期です。七五三は子どもの健やかな成長を願う目的の行事であるため、過度に制限せず、家族の気持ちと体調、スケジュールを最優先に考える姿勢が現実的です。
忌中(四十九日まで)で気持ちの整理が難しい場合は、日程をずらす、会食を控える、写真のみ先に撮るなど、静かな形へ調整すると無理がありません。
また、宗教観によって神社やお寺への参拝の捉え方が異なります。迷う場合は寺社の公式案内や家族内の慣習を確認し、先方の受付方法(予約の要否、混雑時期)を踏まえて決めると安心です。
祖父母としては、判断を急かさず、主催する親の決定を尊重しつつ必要な支援(移動や衣装の手配、写真の受け取り先)を静かに申し出るのが穏当です。
喪中で七五三を控える場合の代替案
喪中で華やかな集まりを避けたい場合でも、成長を祝う気持ちは形を変えて表せます。
時期をずらす
忌明け後や翌年の満年齢の節目に改めて参拝や撮影を行います。混雑を避け、子どもの体力に合わせやすい利点があります。
写真撮影のみ
参拝は先送りにし、貸切型の写真館や静かな時間帯で記念撮影を行います。写真は祖父母への報告にも活用できます。
会食のみ・小規模に
外食を避けたい場合は自宅でささやかな食卓を囲み、後日落ち着いて参拝する二段構えも選択肢です。
お寺での祈願
宗教観に合わせ、お寺でのご祈願を選ぶ家庭もあります。事前に受付方法や混雑時期を確認し、子どもの負担が少ない時間帯を選ぶと良いでしょう。
いずれも、家族が納得できるペースで進めることが鍵となります。
祖父母が控えめに関わることのメリット

控えめな関わり方は、親世代の主体性を尊重しつつ、祖父母の負担も軽減します。準備や当日の進行を親が自分たちのリズムで決められると、衣装選びや撮影プランが子ども中心に整い、結果として満足度が高まります。
祖父母側は役割過多にならず、移動や長時間拘束の負担を避けられます。呼ばれない・控える選択があっても、後日の写真共有や短いメッセージ、ささやかな贈り物で関係性は育まれます。無理をしないからこそ長期的に良い関係が続き、次の行事での協力体制も築きやすくなります。
孫の成長を祝う気持ちは、形を変えても伝わる
立ち会えなくても、祝意は十分に伝えられます。メッセージカードや図書カード、菓子折りなど負担になりにくい品を添えるのも良い方法です。贈る際は「会えず寂しいけれど、成長が何よりうれしい」という軸を一文で添えると、干渉ではなく応援であることが明確になります。
次に会う日程の相談を急がず、電話で当日の様子を聞く時間を持つだけでも、共有感が高まります。要するに、祝う心の伝え方は一つではなく、控えめな形でも温かさは届いていくことでしょう。
七五三に呼ばれない時や喪中時での配慮と心の持ち方
記事のポイントをまとめました。
✅誰と祝うかは家族ごとに異なり主催は親である
✅呼ばれない事実は感情と切り分けて背景を確かめる
✅若夫婦側は連絡は早めに簡潔に理由と配慮を添えて伝える
✅片方だけ招く場合は非招待側への事前説明が要点
✅メッセージカードも気持ちを届ける良い方法
✅当日の写真は祖父母にとっての孫の成長記録
✅お祝い金は負担のない範囲で目安を参考に判断する
✅のし袋は紅白蝶結びと新札で丁寧さを整える
✅お返しは写真や菓子など控えめで十分なことが多い
✅喪中は家族のペースを最優先に形を調整してよい
✅代替案は時期をずらす撮影のみ会食のみなど柔軟に
✅寺社の受付方法や混雑時期を事前に確認して選ぶ
✅祖父母は主導より支援に回ると関係が穏やかに続く
✅会えなくても図書カードや写真で祝意は届く
✅七五三に呼ばれない時も喪中時の七五三も配慮が大事
最後までお読みいただきありがとうございました。


