孫の世話から来るストレスを感じる祖父母は決して少なくありません。急な依頼を断りにくい状況や、体調や疲れを理由にできない現実に直面すると、負担は大きくなります。さらに、子育ての価値観の違いや、いつでも頼られるプレッシャーが重なり、心の余裕を失ってしまうこともあります。
その結果、孫ブルーと呼ばれる心情の正体を抱え込み、断れない、「断る」という言いにくさとの戦いに苦しむ人もいます。加えて、過干渉・価値観のズレを避けられない場面も多く、断ると関係が悪くなる?という不安を抱えがちです。
中には“自分の人生も大切”という思いの抑え込みを強いられ、精神的健康に与える影響が表れることもあります。しかし、自分だけの役割を見つけ、孫の世話の頻度・負担に関するリアルな統計を知ることで、状況を客観的に把握し、前向きに対処する道が開けるでしょう。
本記事では、孫の世話に伴うストレスを理解し、健やかな関係を築くための考え方や工夫を整理していきます。
孫の世話 ストレスを抱える背景とは

- 「娘(息子)からの急な依頼は断りにくい」心理
- 体調や疲れを理由にできない現実
- 子育ての価値観の違いが生む摩擦
- いつでも頼られるプレッシャー
- 「孫ブルー」と呼ばれる心情の正体
- 断れない 「断る」という言いにくさとの戦い
「娘(息子)からの急な依頼は断りにくい」心理

孫の世話は計画的にお願いされるよりも、突発的に依頼されるケースが非常に多いとされています。たとえば保育園や学校の行事、親の急な残業や体調不良など、予期せぬ出来事により祖父母に声がかかる場面は少なくありません。
こうした状況で断るのは心理的に難しく、多くの祖父母は自分の予定を後回しにしてでも孫の世話を引き受けています。
孫を預かる場面では、急に頼まれて準備が整わないまま対応することも少なくありません。こうした突発的な依頼が重なると、気づかないうちに疲れやストレスが積み重なってしまいます。
予定が急に変更されると、趣味や友人との約束を諦めなければならない場合も多く、これが自己犠牲感や不満感につながります。
また、断ることが「冷たい人間だと思われるのではないか」という不安も影響し、心理的な葛藤を生じさせます。その結果、心身への負担が蓄積し、慢性的な疲労やイライラを引き起こすケースもあります。
今後は、家族内であらかじめルールを話し合い、「どのような場合なら引き受けられるのか」「どの頻度が現実的か」といった線引きを明確にしておくことが必要だと考えられます。
体調や疲れを理由にできない現実

年齢を重ねると体力は低下し、疲れや体調不良を感じやすくなります。それでも、子どもや孫のために「体調が悪いから今日は無理」と言いにくい祖父母は少なくありません。親世代に迷惑をかけたくない気持ちや、家族の期待に応えたい思いが働き、無理をしてでも世話を引き受けてしまうのです。
実際のデータからは、祖父母が常に子育ての担い手になっているわけではないことがわかります。
国立社会保障・人口問題研究所「第16回 出生動向基本調査(夫婦調査)」によると、第1子が3歳になるまでに母方祖母が子育てを手伝った家庭は2005〜2009年出生児で50.0%、2015〜2019年出生児では45.7%と半数程度にとどまっています(出典:e-Stat/政府統計の総合窓口 表9-3-1)。
| 出生年区分 | 手助けあり(件数) | 手助けなし(件数) | 手助けありの割合 |
|---|---|---|---|
| 2005~2009年 | 321 | 296 | 約52% |
| 2010~2014年 | 432 | 447 | 約48% |
| 2015~2019年 | 250 | 271 | 約46% |
この数字が示しているのは、祖父母の助けは多くの家庭にとって欠かせない存在である一方で、決して無理をしてまで担う必要はないということです。自分の体調や気持ちを大切にすることが、結果的に家族にとっても安心につながっていきます。
子育ての価値観の違いが生む摩擦
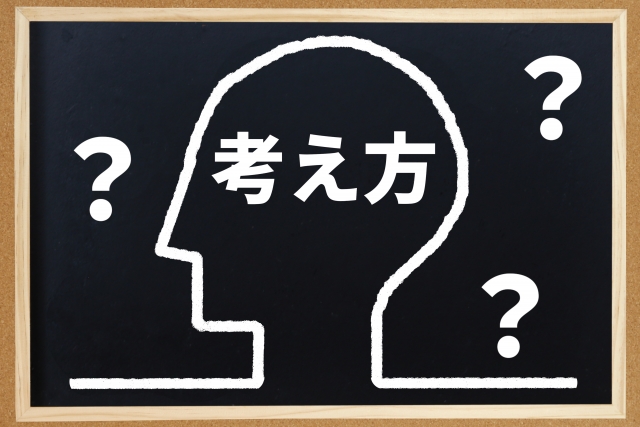
祖父母世代と親世代では、子育てに対する考え方が異なることが多く見受けられます。食事の習慣やしつけの方法、生活リズムに関する意見の違いは、日常の中で摩擦を生みやすい要素です。
祖父母にとっては「昔は当たり前だったこと」も、現代の育児では推奨されていないケースがあり、その違いが否定されたように感じてストレスにつながることもあります。
心理学の研究でも、価値観の不一致が家庭内の葛藤を招く要因であることが示されています。例えば、大学生を対象とした研究では、親子間で価値観が食い違う場面では「親への反発」や「自己優先」の反応が強まる傾向が確認されており、世代間の価値観の違いが対立を生みやすいことがわかります(出典:藤原あやの『親子の対立・葛藤における青年の反応尺度の作成』J-STAGE )。
こうした背景を考えると、祖父母が自分の育児経験を一方的に押し付けるのではなく、親世代の考えを尊重しながら歩み寄る姿勢が家庭の調和を保つカギになります。小さな違いを受け入れる柔軟さが、孫との関係だけでなく家族全体の安心感にもつながります。
いつでも頼られるプレッシャー

内閣府の調査によると、祖父母と孫が「ほとんど毎日会う」家庭が33.2%、「年に数回会う」が24.5%、「月に1〜2回会う」が19.0%と報告されています。(出典:内閣府『高齢社会白書』)
このように、祖父母と孫の接触が頻繁にある家庭は多く、結果として孫の世話に関わる機会が多いことがうかがえます。こうした背景から「いつでも頼られるプレッシャー」を強く感じる祖父母は決して少数ではありません。
常に頼られているという感覚は、次第に義務感へと変化し、やがて自分の生活や自由を犠牲にしてしまう要因となります。休養を取るタイミングを逃したり、自分の趣味や交友関係を制限したりすることで、精神的にも肉体的にも疲弊していくのです。
さらに、過度のプレッシャーは「自分が断れば家庭が回らなくなる」という思い込みを強め、心の負担を一層増大させます。
子育て支援として祖父母の協力は重要ですが、それが「無制限のサポート」となってしまうと、世代間の関係に緊張を生みます。
したがって、家族の間で明確なルールを設け、祖父母の負担を適切に分散させる仕組みを構築することが必要です。たとえば「平日は週に1回まで」「夜間は原則対応しない」といった基準を設けることで、無理のない範囲での協力が可能になります。
「孫ブルー」と呼ばれる心情の正体
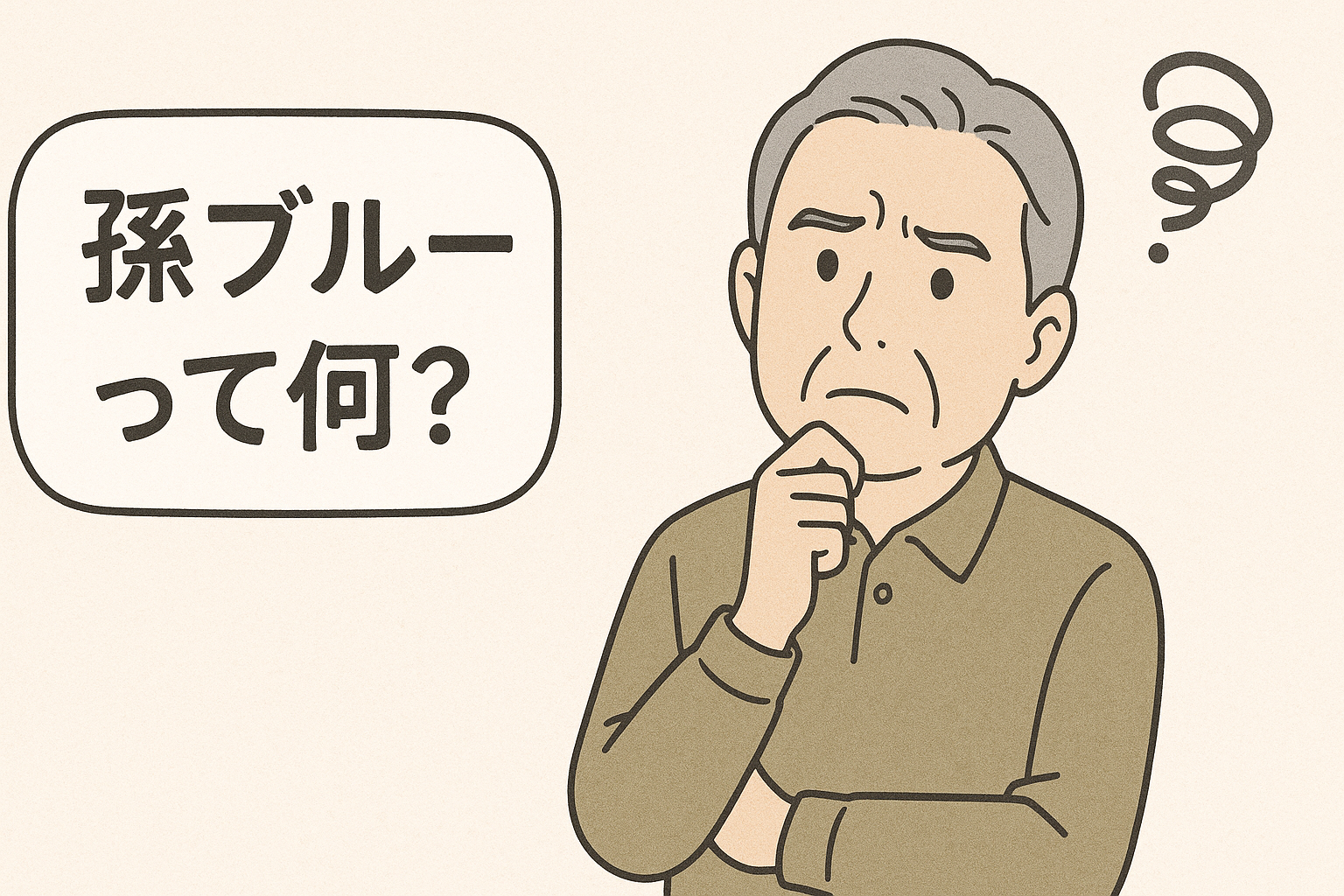
孫の誕生は大きな喜びであるはずですが、その裏側で「孫ブルー」と呼ばれる心情に悩む祖父母が増えています。
これは、孫の世話が期待されすぎることで生活の自由が奪われ、自分の時間を持てないことから生じる憂うつな感情を指します。うつ症状やストレス反応に似た心理状態を伴うこともあり、精神的な負担として見過ごせない現象です。
「孫ブルー」という言葉はまだ社会的に浸透していませんが、心理学や高齢者福祉の分野ではすでに注目されつつあります。特に女性は家事や育児の役割を担ってきた経験から、孫育てに対して「自分がやらなければ」という意識が強く働きやすく、結果的にブルーな感情を抱え込みやすいとされています。
🍀「孫ブルー」に関して【孫育て】疲れたら読んでほしい対策と心が軽くなる工夫 こちらの記事で詳しくお伝えしています。
背景には、世代間の価値観の違いや、社会的に「祖父母は孫の世話をするもの」という暗黙の期待があることも無視できません。実際には、祖父母自身にも健康や生活の課題が存在し、それを軽視することは本人の精神的・身体的な健康を損なうリスクにつながります。
今後は、この感情が一時的な疲労や気分の落ち込みにとどまらず、メンタルヘルスに深刻な影響を及ぼす可能性があることを社会全体が理解する必要があります。
家族内での役割分担を見直すだけでなく、地域や行政の支援を取り入れることが、この課題の解決に向けた重要なステップといえるでしょう。
断れない 「断る」という言いにくさとの戦い

孫の世話を依頼されたとき、多くの祖父母は「断りたいけれど言いにくい」という葛藤に直面します。親子関係における遠慮や、家族に迷惑をかけたくないという気持ちが強く働き、結局は無理を押してでも引き受けてしまうのです。こうした繰り返しが続くと、自分の時間や健康が犠牲になり、ストレスの悪循環に陥ります。
特に日本の文化では「家族を支えるのは当然」という価値観が根強く、断ることを「自己中心的」だと感じてしまう傾向があります。しかし実際には、祖父母が過剰に無理をすれば長期的に見て家庭全体の支えを失うリスクが高まります。心理学的にも、自分の意思を相手に伝えるスキルである「アサーション(自己表現)」は、家族関係の健全性を保つうえで重要とされています。
効果的な方法としては、単に「できない」と言うのではなく、「その日は通院の予定があるので別の日なら可能です」といった代替案を提示することが挙げられます。これにより関係を悪化させずに自分の立場を守ることができます。
さらに、家族会議のような場を設け、祖父母の負担について話し合うことで、無理のないサポート体制を築くことが可能になります。
要するに、断ることは関係を壊すのではなく、むしろ長期的に健全な家族関係を維持するために欠かせない行為です。勇気を持って適切に自己主張することが、ストレスの軽減と良好な親子関係の両立につながります。
孫の世話 ストレスを軽減する視点

- 過干渉・価値観のズレを避ける工夫
- 断ると関係が悪くなる?への不安
- “自分の人生も大切”という思いの抑え込み
- 精神的健康に与える影響を理解する
- 自分だけの役割を見つける方法
- 孫の世話の頻度・負担に関するリアルな統計
- 孫の世話 ストレスと向き合うためのまとめ
過干渉・価値観のズレを避ける工夫

孫の世話に積極的に関わることは喜ばしい一方で、行き過ぎると「過干渉」と受け取られてしまう危険性があります。
親世代と祖父母世代の間には、育児に関する価値観の違いが自然と存在し、食事やしつけ、遊び方に至るまで意見が食い違う場面は少なくありません。こうしたズレを無視してしまうと、親世代が不満を抱き、家庭内に緊張関係が生まれる要因となります。
解決の第一歩は、祖父母が自らの役割を明確に認識し、親世代の意向を尊重する姿勢を持つことです。特に乳幼児期は親の方針が家庭の軸となるため、その指示に沿ったサポートを心がけることが円滑な関係維持につながります。
例えば「おやつの与え方」や「テレビ視聴の制限」といった細かなルールであっても、祖父母の経験や考えを押し付けるのではなく、相談のうえで妥協点を探ることが大切です。
また、柔軟な受け止め方を意識することも重要です。小さな価値観の違いを「自分が否定された」と捉えるのではなく、「時代が変わったのだ」と前向きに受け入れることで、ストレスを軽減できます。世代間のズレを避ける工夫は、最終的には孫にとって安心できる育児環境を整えることにつながります。
断ると関係が悪くなる?への不安

孫の世話を断ることに罪悪感を抱き、親子関係が悪化するのではないかと不安を感じる祖父母は珍しくありません。家族を支える存在としての役割意識が強いほど、依頼を断る行為を「わがまま」と感じやすい傾向があります。
しかし、無理を重ねて体調を崩せば、結果的に長期的なサポートが困難となり、かえって家族全体の負担が増えるリスクを生みます。
効果的な方法は、単に「できない」と言うのではなく、自分の体調や予定を誠実に伝えることです。「今日は友人と約束があるので対応できない」「今週は疲労が強いので来週なら可能」といった説明を加えれば、関係を損なわずに理解を得やすくなります。
信頼関係を維持しながら負担を調整することは、孫との健全な関わりを続けるために不可欠です。
“自分の人生も大切”という思いの抑え込み

孫の世話を優先するあまり、自分自身の楽しみや夢を後回しにしてしまう祖父母は一定数存在します。しかし、このように「自分の人生も大切」という思いを抑え込み続けることは、精神的な負担を増やし、やがて心身の不調につながる危険性があります。
心理学の研究でも、自分の意思で行動できていると感じる「自己決定感」が高い人ほど、ストレスに対して強い耐性を持つことが示されています。
例えば、Liuら(2021年)の研究では、(日本語訳に直すと)自律性・有能感・関係性といった基本的な心理的欲求が満たされると、困難に直面しても回復しやすい、つまりレジリエンスが高まることが報告されています(出典:Liuら『Effects of Basic Psychological Needs on Resilience』2021, Frontiers in Psychology)。
この知見を踏まえると、祖父母が自分の趣味や社会活動を大切にしながら孫と関わることは、決してわがままではなく、むしろ健やかな心を保ち、家族関係を良好に維持するための大切な工夫だといえます。小さな楽しみを生活に取り入れることが、結果的に孫や家族への温かいサポートを長く続ける力につながります。
精神的健康に与える影響を理解する

孫の世話は喜びをもたらす一方で、その負担が大きくなると精神的健康に影響を及ぼす可能性があると言われています。
精神的健康とは、心の元気さやバランスのことで、「病気ではない」というだけではありません。世界保健機関(WHO)によれば、精神的健康とは「人生のストレスにうまく対応でき、自分らしく能力を発揮し、学んだり働いたり、地域に役立ったりできる状態」とされています。つまり、心が元気であることは、家族や趣味、生活を楽しむためにもとても大切なことなのです。
特に高齢者の場合、体力の衰えや生活リズムの変化が加わることで、ストレスが蓄積しやすい環境に置かれています。過度なストレスは、不眠や食欲不振、気分の落ち込みなどの典型的な症状として現れることがあり、慢性化すればうつ症状や不安障害に発展するリスクも否定できません。
心の健康を守るためには、まず「自分の限界を知る」ことが大切です。たとえば「週に何回なら無理なく孫を預かれるか」を明確にしておくことは、過剰な負担を防ぐ効果があります。
さらに、家族内での役割分担を話し合い、サポートの範囲をあらかじめ決めておくことで、無理のない関わり方を実現できます。精神的な不調を防ぐことは、長期的に見て孫や家族との関係を良好に保つ基盤となります。
自分だけの役割を見つける方法

孫の世話に時間を割くことは意義のある行動ですが、それが生活の中心になりすぎると自己喪失感やストレスにつながります。そこで大切なのが「自分だけの役割」を見つけることです。これは、家族のサポートを行いながらも、自分自身の人生に意味や充実感を見いだす方法を指します。
具体的には、趣味を継続する、地域のボランティア活動に参加する、学び直しや新しい習い事を始めるなどが挙げられます。これらの活動は「孫の世話をする人」という枠を超えた役割を与え、自己肯定感を高める効果があります。さらに、社会とのつながりを維持することで孤立感を防ぎ、精神的な安定をもたらすとされています。
家庭内でも、自分の役割を意識することは安心感を与える効果があります。たとえば「孫に昔話を聞かせる役割」「料理を一緒に楽しむ役割」といった形で、自分ならではの関わり方を見つけることは、孫にとっても特別な体験となります。
結果として、世代間のバランスを整えつつ、より豊かな家族関係を築くことができるのです。
孫との関わりは、人生に大きな喜びと活力をもたらします。しかし、無理を重ねればその幸せが負担へと変わってしまいます。だからこそ、家族と健やかな境界線を引き、自分自身の時間や心を大切にすることが欠かせません。境界線を意識して実践することで、祖父母も孫も安心して過ごせる環境が整い、笑顔あふれる関係を築いていくことができるのです。
孫の世話 ストレスと向き合うためのまとめ
記事のポイントをまとめました。
✅孫の世話は急な依頼が多く断りにくい
✅体調や疲れを理由にできず無理を重ねやすい
✅子育て価値観の違いが摩擦を生む場面がある
✅いつでも頼られる状況が負担を増やす
✅孫ブルーと呼ばれる心情が広がりつつある
✅断れない言いにくさが大きなストレス要因
✅過干渉や価値観のズレを避ける工夫が必要
✅断ることは関係悪化ではなく健全な選択となる
✅自分の人生を抑え込むことは心の健康を損なう
✅孫世話の過剰な負担は精神的健康に影響する
✅自分だけの役割を持つことが支えになる
✅孫世話の頻度や時間は統計で可視化できる
✅世話の負担は社会的な理解が求められている
✅祖父母の限界を尊重する姿勢が家族の調和を守る
✅孫の世話ストレスは共有し解決策を探ることが大切
最後までお読みいただきありがとうございました。


