孫が帰ってくるのは、とてもうれしいことですよね。
ただ、にぎやかな毎日が続くと、「ちょっと疲れた…」と感じるのも自然なことです。
▶世代で生活のペースが違う。
▶家の中がいつもよりにぎやか。
▶家事が一気に増える。
▶息子・娘夫婦へも気をつかう。
▶気づけば自分の時間がなくなる。
——こんな積み重ねが、心と体の疲れにつながります。
この記事では、すぐにできる対策をやさしくご紹介します。
「ほどほど家事」「予定を詰めすぎない」「上手に頼る」「遊びゾーン作り」「体力づくり」「リカバリー日」——今日から取り入れられる工夫ばかりです。
- 孫疲れの典型パターンと負担の正体を理解
- 家事と人間関係の線引きで疲労を減らす
- 予定・環境・体力の三方向からの対策
- 帰省後に回復するリカバリー設計
孫の帰省 疲れる原因と実態
- 孫がかわいいけれど「ペースが違いすぎてぐったり」
- 気が休まらない&自分時間がゼロ
- 家事の負担倍増を抑える
- 息子・娘夫婦への気遣いの線引き
- 体力的な疲労のサイン
孫がかわいいけれど「ペースが違いすぎてぐったり」

子どもは朝から元気いっぱい。
歩く速さも、話すテンポも、大人とはリズムが違います。
無理に合わせようとすると、どうしても疲れがたまります。
事前のすり合わせが助けになります。
起きる時間、寝る時間、ごはんのタイミング、入浴の順番などを、ざっくりで良いので前もって共有しておきましょう。
・朝は静かに過ごす/夜9時以降は音量を下げる
・朝食はそれぞれのペースでOK
・お出かけは1日1回まで など
小さな摩擦を防ぐ一言
言いにくいことは、早め・やわらかく伝えると角が立ちません。
「その時間は少し休みたいので、音量を下げてもらえると助かるわ」のように、相手を否定せずに自分の希望を伝える一言が、家庭内の空気を穏やかに保つ鍵となります。
大切なのは、感情的になる前に静かなタイミングで伝えることです。
特に当日の現場で突然伝えるよりも、帰省前の連絡の中で「早寝の習慣があるから、夜は静かにしてもらえると助かる」と前もって話しておくと、受け入れてもらいやすくなります。
こうした小さな配慮が、家族全体の快適度を大きく左右します。
気が休まらない&自分時間がゼロ
にぎやかな状態が続くと、脳も体も休みにくくなります。
普段は静かな生活を送っている方にとって、孫の帰省は喜びである一方で、音・会話・動きが常にある状態は脳への刺激が過剰になり、休息の質が下がりやすくなります。
この状態を防ぐには、「静と動の切り替え」を意識することがポイントです。
リビングとは別に、椅子一脚でもよいので“静かな場所”を作り、深呼吸できる時間をとりましょう。
また、1日のうちに20~30分でも良いので「自分の時間」を固定化するのがおすすめです。
読書、音楽、軽いストレッチなど、心が落ち着く活動を組み込むことで、脳と体のリズムが整いやすくなります。
1日のうちに20〜30分でも、自分だけの静かな時間を作ることが大切です。
私はこの時間に、ホットアイマスクで目を温めるようにしています。
目を休めると、頭の疲れもスッと軽くなる気がします。
「決まった時間に休む」というリズムが習慣化されると、短時間でも深い休息が取れるようになります。
ストレス信号の見分け方
・ちょっとした物音にイライラする
・ため息が増える
・会話の内容を覚えていない、集中できない
・食欲や睡眠のリズムが乱れる
こうしたサインは、心と体が「休息を求めている」信号です。
疲れが強い時ほど、「もう少し頑張ろう」と無理をしがちですが、それが疲労を悪化させます。
「ここで10分だけ休憩するね」と宣言して一度その場を離れることで、心理的な切り替えができます。これは単なる休憩ではなく、セルフケアの一環です。自分を大切に扱う時間を意識的に確保することが、孫疲れを防ぐ第一歩です。
家事の負担倍増を抑える
孫の帰省中は、調理・掃除・買い出し・片付け・洗濯などの家事が一気に増加します。特に、孫が小さい場合は食器や衣類の洗い替えが多く、普段の倍以上の家事量になることもあります。家事を完璧にこなそうとすると、身体的にも精神的にも疲れが溜まりやすくなります。
まず大切なのは、「すべてを自分でやろうとしない」ことです。
家事を小分けにして、家族全員で分担する意識を持ちましょう。
配膳・下膳・食器洗い・洗濯の仕分け・子どもの片付けなど、それぞれの役割を具体的に決めておくことで、作業効率がぐっと上がります。
また、料理は「主菜+汁物」の固定メニューを数パターン用意しておくと、迷わず準備ができます。副菜は惣菜やカット野菜、冷凍食品を上手に使い、完璧を求めすぎないことがポイントです。
帰省前に必要な食材や日用品のリストを作成し、ネットスーパーなどを利用すれば、買い物の負担を軽減できます。
| 負担ポイント | つまずきやすい原因 | 現実的な代替策 | 準備タイミング |
|---|---|---|---|
| 夕食づくり | 人数増で品数を増やしがち | 主菜一品+汁物固定、惣菜で副菜補完 | 帰省の3日前に献立テンプレ作成 |
| 食器洗い | 回数と量の急増 | 食洗機フル活用、紙皿を一部併用 | 必要資材を前日購入 |
| 洗濯 | 子どもの汚れ物が増加 | ネット分けと翌朝一括乾燥 | 洗濯ネットを人数分用意 |
| 片付け | おもちゃ散乱 | カゴ一つに集めるルール | カゴを玄関と居間に配置 |
このように工程を細分化して「誰が・いつ・何をするか」を明確にしておくと、家事負担を実感しにくくなります。
さらに、「15分ルール」を取り入れて、作業を15分単位で区切ると、疲れを感じる前に休憩を挟むことができます。特に高齢世代の場合、立ち仕事を長時間続けると腰や膝に負担がかかるため、無理をしないタイムマネジメントが大切です。
家事を「手抜き」ではなく「効率化」と捉え、負担を減らしながら家族との時間を楽しむ工夫を意識してみてください。
息子・娘夫婦への気遣いの線引き
息子・娘夫婦との関係は、孫の帰省中に最も気を遣う場面の一つです。
良好な関係を維持したい気持ちが強いあまり、「自分が頑張らなければ」と抱え込みすぎてしまう人も多いでしょう。しかし、無理を続けると心身の負担が蓄積し、結果的に関係にも影響を及ぼす可能性があります。
まず大切なのは、「遠慮」と「協力」のバランスを取ることです。家族であっても生活のリズムや考え方は異なるため、最初に役割分担を明確にしておくと誤解を防げます。
たとえば以下のような点を、帰省初日に簡単に共有しておくのが効果的です。
このように言語化することで、相手も判断しやすくなります。「長時間の抱っこは腰に負担がある」「夜の片付けはお願いできると助かる」といった、具体的な依頼の形にするのがポイントです。
育児の方針は親(子世帯)を尊重しましょう。
これにより、相手の自立を尊重しつつも、世代間の摩擦を防ぐことができます。
特に現代の育児方針は多様化しており、祖父母世代の常識が必ずしも通用するとは限りません。

育児に関する価値観の違いが親世代と祖父母世代の間でストレスの原因
伝え方の工夫
伝える順番は、「希望 → 理由 → 代替案」が◎。
例)
「長時間の外遊びは体力的に少し不安なので、午前は公園、午後は室内遊びにしない?」
語尾は「~してもらえると助かるわ」「~だと安心よ」など、やわらかい表現で。
体力的な疲労のサイン
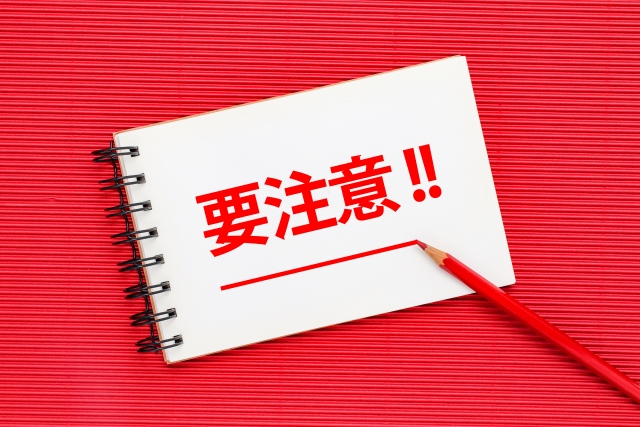
孫の帰省中は、普段の生活では行わない動作や活動が増えるため、気づかないうちに身体への負担が蓄積しがちです。特に、抱っこやお風呂の介助、買い出しや掃除の頻度の増加などは、シニア世代にとってかなりの運動量になります。
以下のようなサインが現れたら、身体が休息を求めている証拠です。
サインが出たら、予定を少し減らす・横になる時間を確保。特に、孫と遊ぶ時間の合間に15〜20分でも横になることで、筋肉の回復と自律神経の安定が促されます。
また、入浴後に軽いストレッチを取り入れると、血行が促進され疲労物質の排出を助けます。無理にマッサージを行うよりも、足首を回したり、ふくらはぎを軽く伸ばす程度が適しています。
疲労を感じたときは、「今日はここまで」と言える勇気を持ちましょう。自分を大切にすることが、家族みんなの笑顔につながります。
孫の帰省でおきる疲れを軽減する方法
- ほどほど家事の推奨を実践
- スケジュールを詰めすぎない工夫
- 年末年始の孫の帰省で疲れないための3つのポイント
- 息子・娘夫婦にも協力してもらう勇気
- 孫が遊べるゾーン作りとリカバリー日を作る
- 体力維持のための努力の習慣
- 孫の帰省 疲れる原因と対処法の総括
ほどほど家事の推奨を実践

家事は、体を自然に動かす日常的な運動のひとつです。
掃除や洗濯、食器洗いといった動作は、立ったり歩いたりする機会が増えるため、全身の血流を促し、筋肉や関節の動きを保つ効果があります。
ただし、長時間の立ち作業や中腰姿勢を続けると、腰や膝への負担が蓄積しやすく、疲労感や痛みの原因になります。
厚生労働省が公表する「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」では、日常生活の中での家事や買い物などの軽い身体活動も健康維持に有効であるとされています。
特に、強い運動を行わなくても、生活の中で“ほどほどに体を動かす”ことが健康づくりに役立つと明示されています(出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」)。
つまり、「家事を完全にこなすこと」よりも、「無理のない範囲で体を動かすこと」に意味があります。
たとえば、掃除は1回15分以内に区切り、料理は惣菜を取り入れて品数を減らす、洗濯は1日おきに回すなど、“がんばりすぎない工夫”が大切です。
「今日はこれで十分」と区切ることで、体にも心にも余裕が生まれ、家事を負担ではなくリズムとして取り入れられます。
完璧を目指さず、“ほどほど家事”を健康維持のひとつと考えることが、孫の帰省シーズンを元気に乗り切る秘訣です。
小ワザでラクにする
✅ タイマーで区切る
・配膳準備の前にキッチンタイマーをセット(例:15分)
・時間が来たら終了!「やる/やらない」の線引きをはっきりさせます。
✅ 鍋・フライパンは“すぐ浸け置き”
・使い終わったら、ぬるま湯にすぐ浸す(洗剤少量でもOK)
・焦げつきが落ちやすくなり、後片付けの手間がぐっと軽く。
✅ 使い捨てアイテムを上手に活用
・使い捨てスポンジやキッチンペーパーを常備
・衛生的で、洗う・乾かす手間を省けます。
✅ 後処理がラクな道具を選ぶ
・軽いアルミ鍋、食洗機対応の皿、フタ付き保存容器など
・「使って→洗って→片付ける」時間を短縮できます。
✅ ワンアクション収納で動線スッキリ
・よく使う道具は手の届く高さに
・“出す→使う→戻す”が一歩で完了。
✅ “ながら”で小掃除
・お湯を沸かす間に台拭き、レンジが回る間にシンクをひと拭き
・1~2分のスキマ時間を使えば、大掃除いらず。
✅ 15分ルールで体を守る
・15分作業したら、3~5分イスに座って休憩
・腰や膝への負担をためない“こまめ休み”を習慣に。
✅ 「十分」を合言葉に
・今日は主菜+汁物で十分。副菜は惣菜にお任せ
・完璧よりも、元気を残すことが大切です。
スケジュールを詰めすぎない工夫

外出や観光を詰め込むと、移動と段取りで疲れます。1日1イベントの原則にすると余裕が生まれます。以下は2泊3日の余裕プラン例です。
| 日程 | 午前 | 午後 | 夜 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 到着・昼食は簡便メニュー | 近所の公園で短時間遊ぶ | 惣菜併用で早めに就寝 |
| 2日目 | 屋内施設か買い出し | 自宅で工作や読書 | 片付けは全員で15分 |
| 3日目 | 荷造りと洗濯前仕分け | 軽い外食で解散 | リカバリー準備 |
ポイントは「移動の長さ」と「音・人混み」の強度を抑えることです。室内遊びや短時間の近場外出を混ぜると、体力の谷を作らずに済みます。
年末年始の孫の帰省で疲れないための3つのポイント
年末年始の帰省は、おせち作りや大掃除、来客対応など、ふだん以上に予定が重なりやすい時期です。
孫の帰省だけでも体力を使うのに、「いつもの家事+年末年始の行事」まで全部こなそうとすると、あっという間に疲れ切ってしまいます。
無理をしないために、次の3つだけでも意識してみてください。
① 大掃除は“やらない場所”を決める
「家じゅう完璧に掃除する」はいったん手放し、「人の目につく場所だけ」「水回りだけ」など、今年は範囲を決めてしまいましょう。気になるところは、暖かくなってから少しずつ掃除すれば大丈夫です。
② おせち・ごちそうは“買う前提”で考える
すべて手作りしようとすると、買い出し・調理・後片付けだけでぐったりしてしまいます。
「黒豆と数の子だけ手作り、あとは買う」「重箱セットを買って、汁物と簡単な一品だけ作る」など、最初から“頼る前提”で考えましょう。
孫にとっては「一緒に食べる時間」がいちばんの思い出になります。
③ 帰省後の“リカバリー日”をカレンダーに確保しておく
孫が帰った翌日は、できれば予定を入れず「洗濯・片付け・お昼寝の日」と決めておきます。
前もってカレンダーに○をつけておくと、「この日まで頑張れば、明日は休める」と気持ちに余裕が生まれます。
年末年始は「がんばるイベント」ではなく、「みんなで無事に1年を締めくくる時間」と考えて、できないことは思い切って減らしていきましょう。
息子・娘夫婦にも協力してもらう勇気
家事や孫の世話を一人で抱え込むのではなく、家族全員で分担する意識を持つことが重要です。「頼ること」は決して甘えではなく、家庭運営の健全な協力関係を築くための一歩です。
依頼する際は、できるだけ行動レベルで具体的に伝えましょう。たとえば次のように分担を明確にすると、相手も動きやすくなります。
- 夕食後の食器洗いとテーブル拭き
- 入浴前の寝間着やタオルの準備
- 寝具の片付けやシーツ交換
また、体力的・経済的な負担を減らすために、外部リソースを積極的に利用するのも賢い選択です。外食やデリバリー、布団レンタル、クリーニングサービスなどを活用すれば、時間の余裕を生み出せます。費用がかかる場合は「家族全員で分担する」という前提で合意しておくと、心理的な負担が軽くなります。
特に近年では、高齢者の家事負担を減らすための支援制度や家事代行サービスも広がっています。(出典:経済産業省「家事支援サービス活用ガイドライン」)
無理をせず、社会のサポートを上手に取り入れることも、現代的な“助け合いの形”です。
断る勇気の持ち方
体調不良や疲労を感じたとき、「今日はここまでにします」と一線を引くことはとても大切です。特に高齢者は、無理をすると回復に時間がかかる傾向があるため、早めの判断が健康維持につながります。
断る際は、余計な言い訳を重ねず、必要最低限の理由に留めましょう。「腰が少し重いので、今日は片付けを明日に回します」「明日は早起きするので、今夜は休ませてください」など、短く誠実に伝えるのがポイントです。
さらに、「代替案を添える」と関係性を損なわずに済みます。「明日の午前に片付けます」「洗濯は分担でお願いします」など、相手の負担を和らげる提案を添えると、受け入れられやすくなります。
頼る勇気と断る勇気の両方を持つことが、孫の帰省を無理なく楽しむための土台になります。家族全員が心地よく過ごすためには、「完璧にこなす」よりも「無理をしない」ことのほうが、ずっと価値があるのです。
孫が遊べるゾーン作りとリカバリー日を作る
リビングの一角を“遊び専用エリア”に。
おもちゃカゴ・絵本・塗り絵・動画コーナーをまとめ、ワンステップ片付け(カゴに入れるだけ)のルールに。
プレイマットや家具の角保護で安全性も確保しましょう。
そして、帰省後は“リカバリー日”を必ず1日。
外出予定を入れず、洗濯・片付け・お昼寝・軽い散歩などで心身を整えましょう。
帰省後のリカバリー日は、体も心もゆっくり整える時間。
私は、この日にホットアイマスクを使って、目元を温めながら静かに過ごすのが定番です。
数分でも、目を休めるだけで気持ちが落ち着きます。
体力維持のための努力の習慣

孫が帰ってくるのを元気に迎えるには、日ごろの体づくりがとても大切です。
年を重ねると、どうしても筋力やバランス感覚が少しずつ落ちてしまいます。
でも、ちょっとした運動を毎日続けるだけで、体力はしっかり守れます。
無理をせず、「できることを少しずつ」が合言葉です。
その積み重ねが、疲れにくい体づくりにつながります。
🔹 毎日の軽い運動を習慣に
厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、
歩行などの中強度の運動を1日40分程度行うことが推奨されています。
個人差等を踏まえ、強度や量を調整し、可能なものから取り組む
今よりも少しでも多く身体を動かす
引用元:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」
時間を見つけて、取り組んでみてはいかがでしょうか。
🔹 ゆるやかストレッチで体を守る
米国スポーツ医学会(ACSM)の報告では、
ふくらはぎ・太もも・背中などの大きな筋肉を、
週に2日以上、ゆっくり伸ばすことがすすめられています。
無理に力を入れず、呼吸を止めないようにするのがポイントです。
筋肉や関節の柔らかさを保つことで、日常の動きがずっとラクになります。
🔹 イス立ち運動で下半身を強く
国立長寿医療研究センターの研究では、
イスからの立ち上がりを10回繰り返す運動が、
足腰の筋力を保ち、転倒を防ぐのに効果的だとされています。
安定したイスを使い、手を使わずに立ったり座ったりしてみましょう。
毎日続けることで、自然と「しっかり立てる力」が身につきます。
(出典:国立長寿医療研究センター「フレイル予防と運動」)
🌷 おすすめのやさしい運動メニュー
✅ ウォーキング
1日20分を目安に、背筋を伸ばしてゆっくり歩きましょう。
✅ ストレッチ
ふくらはぎ・太もも・背中を中心に、呼吸を止めずにゆっくり伸ばします。
✅ イス立ち運動
安定したイスから、立ち上がりを10回くり返します。下半身の強化に効果的です。
🔹 続けるコツ
- 毎日、同じ時間帯に行うと習慣になりやすいです。
例:朝の散歩、昼食後のストレッチ、夕食後の軽い体操など。 - 「頑張る」よりも「気持ちいい」と感じる強さで。
- 少し疲れたら、すぐに休むことも大切です。
🔹 体調と相談しながら
持病や痛みがある場合は、
必ず主治医や理学療法士のアドバイスに従いましょう。
体調に変化を感じたときは、無理せず休むのが一番です。
「毎日少しずつ、長く続ける」ことが、
孫との時間を笑顔で楽しむためのいちばんの準備です。
体を整えて、次の帰省も元気に迎えましょう。
孫の帰省 疲れる原因と対処法の総括
記事のポイントをまとめました。
✅孫の帰省 疲れるの背景は生活リズム差にある
✅音量と就寝時刻など最小限のルールを事前共有する
✅自分時間がゼロにならない20分休憩を固定化する
✅家事は主菜固定と惣菜活用で工程を圧縮する
✅片付けはカゴ一つ方式で子どもも参加させる
✅役割分担は行動レベルで依頼し曖昧さをなくす
✅できないことは短い言葉で線引きし代替案を示す
✅1日1イベントの原則で移動と人混みの負荷を抑える
✅室内遊びと近場外出を組み合わせ疲労を平準化する
✅孫が遊べるゾーン作りで見守り中心の運営にする
✅帰省後は予定を入れず必ずリカバリー日を確保する
✅体力維持のための努力は短時間で毎日続ける
✅水分補給と休憩を習慣化し過負荷を避けて過ごす
✅伝え方は希望と理由と代替案の順で角を立てない
✅無理せず助けを借りる選択が家族全体の満足度を上げる
最後までお読みいただきありがとうございました。


